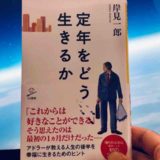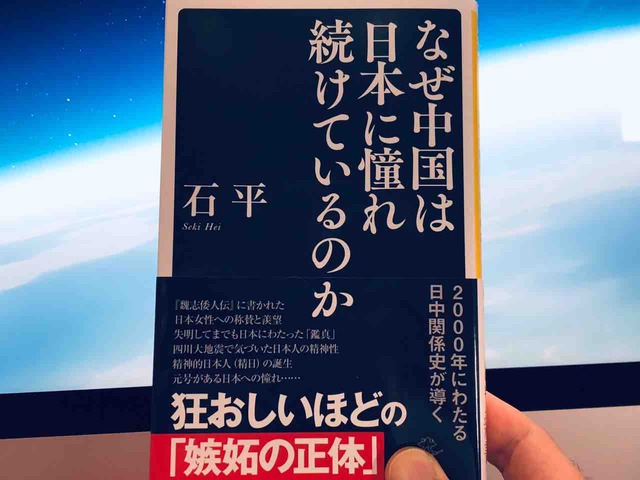
おはようございます!
今日ご紹介する本は、
石 平(著)『なぜ中国は日本に憧れ続けているのか』SB新書
です。
タイトルを見ると「えっ?」となると思いますが、石平氏によると2000年前から中国は日本に憧れを持っているとのこと。
ん〜、どういうとこなんだろ。
まずは早速、気になるポイントの読書メモをシェア!
石 平(著)『なぜ中国は日本に憧れ続けているのか』SB新書:読書メモ
★中華思想の下でも別格だった日本
周知のように、古代から近代に至るまで、中国の歴代王朝と知識人は、いわば中華思想のもとで周辺の民族や国々を完全に上から見下ろすのが普通だった。〈中略〉
しかしその中で中国人は唯一、中国大陸の東の海にある日本列島に対しては、全く別の認識とイメージを持っていたようである。彼らの意識においては、海の向こうにある「三神山」である日本は、文明化されていないわけでは決してなく、むしろ地上の文明を超えたところの神々の世界であり、俗世を超越した仙人たちの棲家となっているからである。
★「改革開放路線」を唱えて日本を頼った鄧小平
現実主義者の彼(鄧小平)は最高権力の座についてから、毛沢東時代の晩期に於いて崩壊寸前だった中国経済の立て直しを何よりもの急務とし、中国経済を成長路線に乗せることを政権の至上課題にした。そこで改革開放路線を唱えて、強力なリーダーシップを持ってそれを進め始めた。
日本には鄧小平が喉から手が出るほど欲しい技術と資金がいくらでもあった。それを中国に引っ張り出すために、鄧小平はいわゆる「領土問題」や「歴史問題」を全部棚上げして、「日中友好」を外交戦略の柱にして、日本との全面的友好関係の構築に努める必要があった。
そこで中国はまず、1978年8月に日本との「日中平和友好条約」の締結にこぎつけた。
★「天安門事件」と反日教育の始まり
大変化の契機は、1989年に中国国内で起きた天安門事件である。〈中略〉
学生運動の鎮圧によって中国共産党政権は難局を乗り越えたが、この時から、共産党政権は新たな危機に直面することとなった。武力を持って学生運動を鎮圧し、愛国の若者達を大量に虐殺した事実が国民の知るところとなり、共産党の威信が池に落ち、同時に共産主義のイデオロギーが崩壊、国民における政権の求心力が完全に失われたからだ。〈中略〉
この時江沢民政権が取った方策は、国民全体を対象とする「愛国主義精神高揚運動」の推進と、これとセットで行った「反日教育」の展開である。
★日本人と同化したい「精神的日本人(精日)」の誕生
あまりにも日本が好きで、「日本人に同化しようとする中国人」も現れてきている。それが中国国内でいう「精日=精神的日本人」である。
「百度」を見ると、「精日」に対する定義は実に簡単で、「精神的に自分のことを日本人と同一視する人々のこと」とある。
ファッションからマナーまで、日本の精神文化に傾倒し、自らの民族的アイデンティティーを変えて日本人になろうとする人のことである。そしてそのほとんどが10代、20代の若者なのである。
★「三つの記念日」で日本を未来永劫叩くことを決めた習近平
3つの国家記念日とは、7月7日の「抗日戦争勃発記念日」、9月3日の「抗日戦争勝利記念日」、12月13日の「南京大虐殺犠牲者追悼日」で、いずれも日本との過去の戦争にまつわる記念日である。
2014年2月開催の「全国人民代表大会(全人代)」は、これら3つの記念日を「国家記念日」と定める法案を採択した。
この3つの国家記念日を制定して以来、5年間、すべての記念日に、中国政府は毎年必ず大規模な国家的記念行事を催して日本批判の気勢を上げてきている。
例えば日本が再度「謝罪」したとしても、中国はこの国家的記念日を取り消すようなことは絶対しない。なぜなら記念日を制定した時点で、習政権はすでに歴史問題を使って日本を未来永劫叩いていくことを、国策として決めていたはずだからだ。
★習近平が唱える「民族の復興」の意味
「中華民族の偉大なる復興」とはつまり、中華民族が近代以来体験した、屈辱の歴史を精算した上で、近代以前の中華帝国の栄光なる地位を取り戻すことである。つまり中国はこれから、再び世界ナンバーワンとなってアジアに君臨し、中国を頂点とした「新華夷秩序」を再建していかなければならないと考えている、ということである。
★習政権の対日改善の理由
日本に対してあれほど敵対政策をとり続けた習政権は、いったいなぜ「対日協調」へと方向転換したのか。
その理由の1つは、まさに今展開中の米中冷戦にある。それこそが中国伝統の外交戦術の1つであるが、北京はワシントンと喧嘩したり対立したりするときは、必ずや日本に接近して、日本と「良い関係」を作ってみせることでアメリカを牽制するのである。
もう一つの理由は、やはり「一帯一路」である。前述のように、2018年から習政権推進の「一帯一路」構想は、欧米では厳しい批判にさらされ、アジア諸国にもそっぽ向かれている。
こうした状況下で中国は、日本との関係を改善した上で、やはり日本の政府と日本企業を一帯一路への参加に引っ張り出したいと思っているのだ。
石 平(著)『なぜ中国は日本に憧れ続けているのか』SB新書:感想
◆日本は「三神山」として憧れの対象だった?
本書は歴史を古代から現代に時系列順にトピックスを追って書かれています。
しかし、今回の読書メモでは戦後の部分に焦点を当ててピックアップしました。
実は本書のテーマの起点となるのが徐福伝説。
徐福が秦の始皇帝のために不老不死の薬を海の向こうにある三神山に取りに行く話で、どうも実際に彼は日本に渡ってきたようです(確証はない)。
その三神山と日本がオーバーラップしていて、古代から日本のことを中国は特別視していたというのです。
が、この説は僕自身なんとも判断しかねるわけで、一応トピックスとしてメモにあげましたが、今回は現代の方にフォーカスさせていただきました。
中華思想では「世界の中心の華のある国」が中国であって、そこから離れれば離れるほど野蛮人の国。なので、周辺国にかなり悪い意味の漢字をあてます。
「匈奴」とかね。
で、古代日本は倭国ですが、「倭」はよく「1人称代名詞”わ”による」という説が有力ですが、「背が丸く曲がって低い人のこと」という説もあります。
別称でないのかどうかは定かではありません。
◆第3の視点からの日中関係
さて、本書で本当に読んでもらいたいのは戦後の部分。
今現在、どうして中国は激しい反日感情を持っているのかというところです。
戦前の中国からの留学生たちの日本に対する屈折した感情。
そして彼らが帰国後指導者となったタイミングで日中戦争に突入します。
もちろん、日中戦争こそが反日の感情の源なわけですが、ご存知の通り日中国交正常化してしばらく(1980年代前半)は「歴史問題」とそれに付随して「靖国参拝」に関しても、今のように激しく抗議するようなことはありませんでした。
(ちなみに尖閣の「領土問題」は、地下資源があることがわかったのち、1971年から急に中国も領有権を主張するようになりました。)
むしろ、日本ブームが起こったぐらい。
それが反日に向かっていくのは、天安門事件以後、中国共産党による国策の成果だったわけです。
このあたりの歴史の流れが本書では非常にわかりやすく解説されています。
そして、中国出身の石平氏によって書かれているということが、非常に貴重。
なぜなら、このテーマを日本人が書くと、どうしても左右の立ち位置からバイアスがかかってしまい、さらに中国からの視点がない。
その点、中国出身で日本をよく知っている著者だからこその”第3の視点”で語られている現代日中関係の変遷とポイントは、われわれにとって重要な示唆をもらえます。
例えば、「精日」という存在は、僕は初めて知りましたが、日中関係がこれだけギクシャクしている中でも、少数派とはいえ「精日」を自称する人たちが出現していることは、今後の日中関係を考える上で一つのヒントを示していると思います。
両国にとって明るい「萌芽」となればいいですが、現実はやはり以下のことをしっかり認識しないといけないでしょう。
すなわち、
中国共産党は今現在も反日教育を行っており、今後も国策として続けていくこと。
それが「中華民族の偉大なる復興」のための施策であること。
中国国内のインターネットは完全に管理下にあり、情報が浸透していくことでの「雪解け」は残念ながら期待できないこと。
こういった現実を本書でしっかりお読みください。
本書はSBクリエイティブ様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
第1章 2000年前から中国に憧れられる国日本
第2章 中国人が模範にした明治日本
第3章 中国はいかにして「反日国家」になったか
第4章 日本人との同化を望む「精神的日本人」の誕生
第5章 中国は今、日本の何に憧れているのか
第6章 習近平政権のアジア支配戦略と反日的体質
関連書籍
石平氏の新刊はこちら