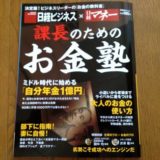おはようございます、毎朝起きてすぐオリンピックの結果を見るのが日課になっている一龍(@ichiryuu)です。
今日は、男前のうえにばんばん新刊を出し続ける底なしに引き出しを持っている、中谷彰宏さんの本をご紹介。
【目次】
はじめに 登りは発散、下りは充電。
第1章 人生の意味に、気づこう。
第2章 しんどいことを、楽しめる。
第3章 前向きな努力を、しよう。
第4章 ほめられないことを、しよう。
第5章 好きなことを、徹底的にする。
おわりに メッセージは、受け取る人の心の中にある。
【ポイント&レバレッジメモ】
★ 03 意味は、あとからついてくる。
多くの人が何かを始めようとする時にちゅうちょするのは、「10年頑張って意味がなかったら、その時間、お金、労力精神的な頑張りがムダになる」と思うからです。
意味を求めるのは、意味がなかった時にムダになるという心配があるからです。
それは無用な心配です。
自分がやりたいこと、好きなことを実現し、形にしている人は黙々とやっています。
黙々とやっていると、どんなことでも意味がついてきます。
そこに迷いはありません。
意味のないものは1つもないからです。
宇宙に存在するありとあらゆるものには、すべて意味があります。
始めていないから、そのことに気づいていないだけなのです。⇒ 意味を、先に求めない。
★ 18 徹底的に無条件で、応援してあげる。
誰かを応援することは、正しいから応援するのではありません。
正しいか間違っているかではありません。
「君がやろうと思っているんだから、間違ってるかもしれないけれど、いい」と言ってあげられることが大切です。
正しい時は応援して、間違っている時は応援しないというのは、応援ではありません。
「ひょっとしたら間違っているかもしれないけれど、応援するわ。だって、君がそれをやりたいと言っているんだもの」と言ってあげることです。⇒ 無条件にする。
★ 20 落ち込むことで、魂の底が広がる。どん底ほど、豊かになれる。
大きな志で小さなことを大切にするのは、ゴムを伸ばしている状態です。
魂は、石でも木でもなく、ゴムでできています。
ゴムを広げていくことが大切です。
下り坂に入っていくのは、魂を広げているのです。
途中でとめたら、魂は大きくなりません。
小さい魂のままでは、何か事が起こった時にそれを受け入れられません。
だからしんどいのです。⇒ きちんと落ち込む。
★ 34 手間をかけた分だけ、価値がある。
夢をかなえたいなら、人と同じことをしないことです。
人の倍儲けようと思ったら、人の倍しんどいことをします。
きわめて単純な原理です。
3倍の値段で売ろうと思ったら、3倍の手間をかけます。
3分の1の手間にしたら、3分の1の値段になります。
きわめて平等です。⇒「あとひと手間」かける。
★ 37 好きなことをしても、ほめられない。
「好きなことをやる」と「やいやい言われる」は、ワンセットです。
最初からほめられていたら、それはほめられることが動機でやっています。
本当に好きなことは
「いったいどう思っているんだ」
「前からいっぺん言おうと思っていた」
「それでいいと思っているのか」
「いいかげん目をさませ」
と、まわりから反対されて、叱られて、説教されます。
それが好きなことをやっている証拠です。
それを言われたら、「自分は間違っていない」と思えばいいのです。⇒「反対されること」をする。
★ 50 「徹底」することで、仕事の満足度が上がる。
好きなことは徹底的にやります。
徹底的にやることで、物事は楽しくなります。
中途半端にやることが一番楽しくないのです。
「楽しくない」「面白味がわからない」「迷いがある」というのは、やり方にどこか徹底さが足りないのです。
「もういいよ」というところから、もう少しだけやってみます。<中略>
徹底することで、自分の仕事への満足度が上がります。⇒ クレイジーなほど徹底的にする。
【感想など】
本書の冒頭に
「この本は、3人のために書きました。」
1. クヨクヨが、頭から離れない人。
2. 今やっていることの意味がわからない人。
3. クヨクヨしている人を、元気づけてあげたい人。
とあります。
が、この本の紹介記事の冒頭でこんなことを言うのもなんですが、ワタクシ、全くクヨクヨしない人間なのです。
(クヨクヨしている人を、元気づけてあげたい人として読みました)
いや、もちろん普通の人間ですから仕事でもプライベートでも、失敗もするしうまくいかないことも多々あります。
でもそういうときに一瞬落ち込みはするものの、クヨクヨはしません。
すぐに、解決できる方法を考えることに全力を注ぐか、絶対無理とわかったらさっさと撤退してしまうからです。
これはビジネス書を読んで身につけた部分もあるのでしょうが、多分若いときに格闘技をやっていたおかげだと思います。
難しい投げ技や関節技をはじめて習ったとき、いろいろと説明してもらっても微妙なコツというのは言葉では伝わりません。
だから先生に何度も何度も投げられて、技をかけられて必死でワザを盗むのです。
先生がどこに力を入れ、どの方向に関節を決め、どのタイミングで崩しに入っているのか?
理屈とかは抜きに、とにかく何度も技をかけてもらう。
するとそのうちに「こうじゃないかな?」というヒントが見えてくる。
そうすると、自分も技がかかり始めます。
その間、考えるよりも行動し続けています。
投げられ、兄弟弟子と試し、また先生に投げられ・・・
投げられるときの自分の身体感覚の復元作業に集中します。
ある程度自分も技がかかり出すと、はじめてそのワザの原理や理屈も見えてきます。
この段階から”考え”始めます。
最初の段階で「難しいなぁ」とか「できなかったらどうしよう」とかまったく考えませんし、そんなことを考える前に体が動いています。
多分スポーツ全般、こんな感じじゃないでしょうか。
クヨクヨしている暇はないのです。
クヨクヨしている代わりに行動するのです。
本書を読んでいると、キーワードは「意味」という言葉だと気づきます。
著者は「意味」=「メッセージ」というとらえ方をしていますが、いずれにしても、冒頭部分の「意味は、あとからついてくる」とか「やっている最中は、意味がわからない」とか「意味は、気づきの中にある。」といった言葉、すごくわかります。
意味なんてやる前からわからない、行動の後から意味はついてくるし、行動してはじめて気がつく、あるいは行動が意味を生み出すものなのです。
今、クヨクヨしている人、だまされたと思ってなにも考えずに行動してみてください。
行動したけどうまくいかずにクヨクヨしている人、今までの倍行動してみてください。
それでダメなら、またクヨクヨするまえにさらに倍行動してみてください。
それを繰り返しているうちに、いつかふと気がつく瞬間がきます。
「あれ、うまくいったやん!」という瞬間です。
このポイントを超えたとき、意味を考えるといいと思います。
だまされたと思ってやってみてください。
そして、だまされたと思って本書を読んでみてください。
きっと、だまされませんから。
本書はあさ出版編集者、吉田様より献本していただきました。
ありがとうございました。