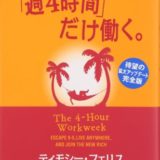<楽天ブックスはコチラ> 『結果を出し続けるために』
羽生名人といえば誰もが認める天才棋士。
七冠達成、19年連続王座などなど輝かしい戦績。
本書ではその対局中の決断方法やミスのリカバリー、そして名人の人生観なども学べます。
さすが真剣勝負の世界で生きてこられた方、とても深いです。
【目次】
はじめに
第1章 努力を結果に結びつけるために
第2章 ツキと運にとらわれずに、最善を選択する
第3章 120%の能力を出し切る、プレッシャーとの付き合い方
第4章 結果を出し続けるには、ミスへの対応が鍵になる
第5章 自ら変化を生み出し、流れに乗っていくために
おわりに
【ポイント&レバレッジメモ】
★勝負で大切なこと
①恐れないこと
経験を積むと、いろいろなことが見えてきて、実際には目に見えないものにおびえてしまい、思い切って踏み込めないことがあります。いつもなら簡単にできることでも、恐れを持ってしまったために自信や決断が鈍って、うまくできないのです。<中略>
自分にとって必要でないものを見極めたうえで、決断しながら不要のものを捨てていくことが、恐れないことにつながるのです。
②客観的な視点を持つこと
局面を、自分の側、相手の側からではなく、審判の様に中立的に見ることです。そうすると、「これはファールだ」「これは誤審だ」「こちらに非がある」といった正しいジャッジができます。言葉を変えると、「他人事のように見る」ということです。
③相手の立場を考えること
「三手くらい、プロなら読むのは簡単ではないか」といっても、実際には難しいのです。最も大事なのが、二手目の相手の指す手をどう読むかなのですが、ここで相手の立場に立つことは非常に難しいからです。自分にとってベストの手を指した後で、今度は相手の立場に立ってベストの手を選択する。つまり自分にとって一番不利な手を考えることが、困難だからです。
★次の一手の決断のプロセス(直感・読み・大局観)
①直感・・・ 80通りの手から、カメラのピントを合わせるように2~3の可能性に絞り込む
②読み・・・ 次の手をシュミレーションする
③大局観・・・ 全体的な方向性や方針をつかむ
◇大局観では「終わりの局面」をイメージする
一局の終わりの場面をイメージするとき、私はよく大局観を使います。「終わりの局面がこうなってくれていたらいいな」「こうなるのではないか」という仮定を作って、そこにつじつまを合わせていく、というようにです。いわば「ハッピーエンド」の状態を想像するのです。
★プレッシャーがかかっているときは八合目まで来ている
将棋の対局でのプレッシャーに関しては、実は、少し不利な時の方が気持ちとしては楽です。なぜなら、不利な時は自力ではどうにもならず、相手のミスを待つしかない、他力本願な局面だからです。
自力ではどうしようもないために、ある意味気楽になって、いつ投了しようかと考えたりします。だからこそ、よい意味で開き直って気軽にさせますし、もともと、分が悪いからこそ、思い切って大胆な一手を指すこともできます。プレッシャーがかかっている時というのは、山登りにたとえると、もう八合目のいいところまで来ているような状態です。しかし、自分の状態を俯瞰できないので、あと少しのところでひるんでしまう、ダメだと思ってしまうケースが非常に多い気がします。
★集中するためには、刺激を遮断する時間を作る
集中力をコントロールするコツとして知っておくといいのは、本当に深く集中するためには、ある程度の助走期間、時間が必要だということです。やはり急には集中できないので少しずつ、集中が深い状態にしていくのです。
また、私は集中するためには、少しくらい疲れている方がいい、と感じています。無駄な力が入らず、雑念も入らないので、余計なことを考えなくてすむからです。<中略>
普段の生活の中で、ボケーッとするというか、ぼんやりして何も考えない時間を持つことも良いでしょう。<中略>何も考えずに頭に刺激が入らない状態にすることです。
★ミスについて
◇ミスへの対処として2つの大切な点
①ミスをどのように割り切るか、受け止めるかというメンタル的な要素
②ミスをしてもそれ以上傷を深めない、大きなダメージを被らないようにするというリカバリー、フォローのやり方
◇ミスをしたときの5つの対処法
①まず一呼吸おくこと
②現在に集中すること
③優劣の判断を冷静に行うこと
④能力を発揮する機会だととらえること
⑤すべてに完璧さを求めないこと。自分の可能性を広げるチャンスだと、とらえること
◇ミスを減らすには
誰でも、その人特有の同じようなミスを繰り返す傾向が強いものです。それゆえ、自分のミスの傾向を知っておくのが、ミスを少なくするコツです。将棋でも同じようなミスをおかしていないかどうかを、指し手ごとに確認すれば、それだけでもかなりのミスを減らせるでしょう。
★才能とは
よく世間で、すばらしい成果を出す人のことを、「才能がある」「この人は天才だ」と言いますが、私は「才能とは、続けること」だと考えています。
プロとアマチュアの違いを定義するならば、「自分の指したい手を指すのがアマチュア」、「相手の指したい手を察知して、それを封じることができるのがプロ」です。
そして、一人前のプロと、一流のプロとの違いは、「継続してできるかどうか」。この一点のみです。
★成功とは
「成功」とは、日々の暮らしの中で、出会った人や所属している組織やグループと、自分とがマッチしていること、ぴったり一致していることだと私は考えています。<中略>
私はさらに究極的には、「成功とは、今ではなく晩年どうなるか、ということに尽きる」と感じています。
【感想など】
まず、この本を読み終わっての率直な感想ですが、ワタクシかなりプロの棋士さんのことを誤解しておりました。
また、特にこの本の著者、羽生名人クラスの方に関しても。
ワタクシ、プロの棋士さんというのは頭の中で数千通りの指し手がバーっと映像で浮かんで、右脳をフル回転させている人だとばかり思っていました。
そして羽生名人クラスになったら、生まれつきの才能と、とてつもない集中力でミスなんてしないで圧勝なんだろうと。
ところが本書を読んでそれは大きな誤解だと気がつきました。
まずプロの棋士でも三手先を正確に読むのは難しいということ。
そして、やっぱり人間なんですよ、あたりまえですが。
といってもプロはプロ。
真剣勝負の世界で対局中、どのような意思決定をしていくのか、そのプロセスと、気持ちの持ち方、ミスへの対処など大変興味深く読ませていただきました。
総じて感じたのは“気持ちの切り替えのうまさ”。
自分が有利に展開しているときはいいとして、不利な状況は自分ではどうしようもないから開き直る。
この考えは面白いですね。
「人事を尽くして天命を待つ」ではないですが、じたばたしても仕方がない状況を見極めるのもプロとしてやっていく上で必要なスキルなのでしょう。
また、うまくいっている時の方がプレッシャーを感じる。
これもまたおもしろい。
こうした試合観などはビジネスパーソンにも通じるところがあると思います。
是非参考にした見てください。
また、本書後半、 第5章 自ら変化を生み出し、流れに乗っていくために では、羽生名人の“人生観”が垣間見られます。
この中で
「人は、ふつうに続けられることしか続かない」
「才能とは、続けること」
「成功」とは、自分のやりたいことと周囲の期待が一致すること
今いる場所や集まりと、自分が調和するためには「周りを裏切らないこと」「自分を裏切らないこと」
この一連のフレーズに惹きつけられました。
この一連のフレーズはすべてリンクしていますよね。
“続けられること”つまり好きなこと、得意なことしか続かないのです。
そして、続けていくうちにそれは“才能”として開花するのです。
しかし、才能として開花しても、それが周りが自分に期待することでないと“成功”はない。
そのためには周囲の人を大切にし、自分も大切にする。
ワタクシにとって“続けられること”ってなんだろう?
周りから期待されていることってなんだろう?
このブログ?
続くかなぁ、誰か期待してくれているかなぁ?
「八面玲瓏」の境地で大局を見てみよう。
羽生名人からの問題提議、深いです。
本書は日本実業出版編集者、滝様より献本していただきました。
ありがとうございました。
【関連書籍】