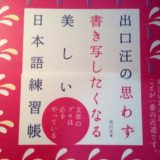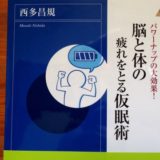おはようございます、一龍です。
今日ご紹介するのは、経済が苦手な方へ超おすすめの入門書。
著者は代々木ゼミナールの人気講師、蔭山克秀さんということで、語り口がめっちゃ面白くてわかりやすい。
はっきり言って、これはスゴ本です!
はじめに
とにかく面白くしかもわかりやすい経済史入門書です。
経済通史の入門書として文句なしのナンバーワンです。
まずは私自身がこれまでよくわかってなくて、本書を読んで「そういうことだったのか」と納得できた点をポイントに挙げましたので、それを御覧ください。
戦後の経済のポイント
★結局、第2次世界大戦の経済的要因とは何か?
結局分かったことは、通貨価値の混乱からくる世界貿易の縮小こそが、第二次世界大戦の経済的な主要因だったということだ。
もちろん政治的にもいろいろな要因があったとこもわかったと思うけど、経済的要因の方はここまでシンプルな太い軸にまとめることができるんだ。
ならば今後、戦争を経済の側面からなくしたいと思うなら、どうするか?
そう、通貨価値の混乱を避けるため、通貨の価値をガッチリ固定させることだね。だから戦後の通貨体制は、「固定相場制」から始まるんだ。
★IMFは世界の通貨体制の守り神だ!
IMF(国際通貨基金)は、戦後の国際通貨体制の守り神として設立された。その目的は、戦争の経済的要因を、通貨の側面から除去することだ。それを実現するために、IMFは次の3つを目指している。
1.為替の安定
「固定相場制」を導入
2.為替の自由化
「為替制限を禁止する」(発展途上国には例外的に認めている)
3.国際収支の安定
「国際収支赤字国への短期融資」
★アメリカが世界の通貨を守る
実は、(大戦後の)固定相場制の正体は「アメリカ一国に依存する変形の金本位制」なのだ。だから固定相場制のことを、別名「金ドル本位制」という。
まずこの体制下では、米ドルを基軸通貨とする。基軸通貨とは貿易用の中心通貨という意味だから、これからは世界中の国々は、基本的に米ドルで貿易の決済(支払い)を行うことになる。交換比率は「金1オンス(28.35グラム)=35ドル」だ。さらに他国通貨は、すべて「1ドル=いくら」で表示する。
するとどうなるか?なんと世界の通貨すべてを、間接的に「金何グラムの価値」で示すことが可能となるのだ。しかも他国は、どの国も交換用の金なんか1グラムも準備する必要はない。これは画期的システムだ。
★資本主義の妖怪にはケインズ経済学では太刀打ちできない
二度の石油危機を経て、世界は一つのことに気づいた。ケインズ経済学の限界だ。
ケインズの「有効需要の原理」は、確かにかつて世界の救世主だった。でもそれは、石油危機から世界を救うのには役に立たなかった。
なぜか?それは石油危機がスタグフレーションを伴うからだ。
スタグフレーションは、「不況÷インフレ」という、本来なら結びつかないはずの二つが結びつく、資本主義の妖怪の一種だ(普通は好況時にインフレ、不況時にデフレが起こる)。
で、石油危機はそのスタグフレーションをもたらす。なぜなら、石油が足りないことで産業が停滞し(=不況)、石油が高いことで全商品の輸送コストが跳ね上がって商品価格が高くなる(=インフレ)からだ。
ということは、ケインズ型は無理でしょ。だって、ケインズ型の本質は「不況時の金のバラマキ」だから、スタグフレーション時にこれやって金をバラまいたら、インフレ部分がさらにひどくなって手の施しようがなくなる。
★人類がこれまでシャブをうまく使えたことはない
実はITバブル崩壊後、アメリカは日本みたいな深刻な不況には陥らなかったのだ。
なぜか?それは不況対策・テロ対策でFRBが行った低金利政策がもとで、アメリカはカネがだぶつき、今度は不動産を中心としたバブルへと移行したのだ。
バブルに続くバブル。もう呆れるべきか羨ましいのかわからん。でも何にせよ二種類のバブルを連続させたおかげで、アメリカは「クリントン→ブッシュ期の最後」まで、切れ目なく好況が続いているように見えたんだ。
でも、バブルは必ず弾ける。歴史上バブルは何度もあったが、弾けなかったバブルは一つもない。格言みたいだが、”カネ余りあるところバブルは起こり、期待感しぼむところバブルは弾ける”だ。
僕ら日本も経験したが、不況対策に不自然な低金利を継続させてバブルを誘発するパターンは、肉体的苦痛に耐えかねてシャブに手を出すようなものだ。効き目は抜群だが、後には必ず地獄が待っている。
★ギリシア問題でズタボロになった日米欧の”最弱争い”
EU加盟国の場合、一国の信用低下は、ユーロ全体の信用低下につながる。<中略>諸外国が「ギリシアと関わりたくない=ユーロと関わりたくない」と思うわけだ。リーマン・ショックのたとえでいうなら、今度はギリシアがサブプライム証券、つまり”腐ったみかん”状態になったわけだ。
この後、当然ユーロの価値は下落し、そのせいで円が相対的に押し上げられてしまった。その結果、日本は2011年に「1ドル=75円」なんていう超円高になったんだ。
こんなのありえないでしょ。だってバブル後の”失われた10年”がそろそろ”20年”になり、東日本大震災でさらに景気がド凹みした国の、一体どこが良くて円が高いの?<中略>
これは簡単に言うと、三大通貨のうちの二つが虫の息になったから、それよりは満身創痍の若頭の方がわずかにマシという判断だ。なにが三大通貨だ、ただの最弱争いじゃん。
★「アベノミクス」
アベノミクスとは、本格的にデフレ脱却をめざす「リフレ政策」だ。
リフレとは「通貨再膨張」のことだ。この政策では、インフレ目標(インフレ・ターゲット)を2%と設定し、そこに到達するまで、意図的に通過を増やし続ける。目標到達まで決してやめない。どんどん増やす。市場にもそうアナウンスし続ける。そうすることで、世の中からデフレ状態とデフレ心理を一掃する。
これがアベノミクス。以上。
て、おい!あっさりしすぎだろうが!と言われそうだが、本当にアベノミクスはこれだけだ。
アベノミクスは、日本機の長期に渡るデフレーションのいちばんの原因を「デフレ・マインド」(不況でカネがないときのショボくれた心理)ととらえ、それが「インフレ・マインド」(好況期の無敵モード。イケイケ心理)に変わるまで、怖くても無制限に金融緩和を続けていくという、ただそれだけの、シンプルだけど狙いが非常に明確な政策だ。
感想
◆文句なしに激オススメ!
今年も残り僅かになりましたが、キタキタ来ましたよ。
私も含めて経済苦手という人に激オススメ作品の登場です。
著者の蔭山先生は代々木ゼミナールの公民科ナンバーワン人気講師ということですが、さすがです。
その講義そのものの語り口で経済史を解説してくれていて、めちゃめちゃ面白いと同時に、読み出したら止まらない。
内容のレベルとしては経済に詳しい方には「そんなこと知っているよ」と言われそうな入門レベルなのですが、ここだけの話、巷の経済本って面白くないですよね。
社会人として最低限知っとかないと恥ずかしいという思いから、これまで経済入門書を何冊か読みましたが、たいてい5分で眠くなるものばかり。
特に大学の先生が書いた本はいけません。
プライドがそうさせるのか、平易に書けないのかわかりませんがどうも今ひとつ難しくて取っ付きにくい。
ところが本書は読み出したら止まりません。
300ページ超えのボリュームですが、一気に読めます。
これまで経済ボンで挫折した皆様へ、一龍の太鼓判!
この本なら読めます、しかも理解できます!
◆現代史はお金で動く
本書は「経済史」ということで、下記の目次の項目を見ていただいたらわかるように、封建制の時代から始まって、現代までの主要なトピックスを解説してくれています。
しかし、読みどころはなんといってもイギリスが絶好調の第1次世界対戦前から現代までの約100年の流れ。
とにかくこの100年のめまぐるしい変化と言ったらない。
変な言い方ですが、「人類史上最も忙しい100年」だったということが経済の側面から見て取れます。
そしてもうひとつ言い方を変えれば、「お金に振り回された100年」とも言えるんじゃないかと思います。
というのも、本書を読むと経済というか、”お金”とそれにまつわる制度こそが世界を動かしているといのがはっきりわかるのです。
あの、2回の大戦も、全体主義とか様々なイデオロギーが表面上は目立ちますが、結局そういった思想も”お金”が生み出したものなのです。
先の大戦で多くの我が国の先輩方が「お国のために」死んでいったわけですが、突き詰めていくと「お金のため」だというのがわかってしまうのは、なんとも悲しいですね。
お金は人を幸せにするツールとして使いたいのですが、諸刃の剣なのです。
◆経済はまだまだ完成ではない
さて、もうひとつ本書を読んで感じたこと。
それは「経済は今なお実験中。完成ではない。」ということでした。
戦後の世界経済が、戦争を起こさないようにとい観点からスタートしたことはわかりましたが、すでに現代のシステムは当時から大きく変わっています。
そして何度もバブルを経験し、コントロール不能という現実を突きつけられています。
しかも、先進国は満身創痍の状態。
今後も困った事態にいつなるかわからないまま未来へと進んでいき、その都度経済の仕組みを改変していくしかないのでしょう。
まさに経済って生き物なんだなとといのが強く実感出来ました。
まぁ私なんかが経済誌を知ったからといって世界の経済システムが変わることもないのですが、これからの時代を生きていく上で知っておいてほしい内容がここには書かれています。
良くも悪くも世の中を動かしているのは”お金”だということ。
そしてこれまでにその”お金”が2度も大戦を引き起こしたこと。
ここだけはしっかり認識しておきたいですね。
ということで、もう一度言いますが、本書は激オススメ!
経済苦手でこれまで経済史を避けてきた人、これなら読めます、わかります!
本書はダイヤモンド社編集者の市川様から献本していただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに 経済史は「欲望のドラマ」だ
講義の前に 1300年間のピカレスク・ロマン
第1章 8〜19世紀半ば 今の弱肉強食社会はどのように生まれたのか?
第2章 19世紀半ば〜1918年 国獲りゲーム勃発!新たな領土を求める仁義なき戦い
第3章 1919〜1945年 やっぱりカネ、カネだ!カネの流れを巡って史上最大の抗争へ
第4章 1940年代後半 ついに組長交代!戦後を牛耳るジャイアン体制とは?
第5章 1940年代後半〜1960年代 一触即発で抗争間近!? 東西組長のにらみ合い
第6章 1970年代 親分負傷で戦々恐々!世界を飲み込む新たな資本主義の妖怪
第7章 1980年代 若頭も組長に立候補!?死に体の親分を踏みつける日本の下克上
第8章 1990年代 カネが分ける新旧の明暗!?グローバル化する抗争劇の勃発
第9章 2000年代 親分は重体、オジキは仲間割れで、抗争は血みどろ地獄へ
第10章 2000年代 ついに世代交代!?ニューフェイスが続々組長に立候補
第11章 2001年〜現在 瀕死の日本はアベノミクスで再起できるか?
巻末付録 主要な経済学説
おわりに
関連書籍
同著者の既刊本を幾つか紹介。