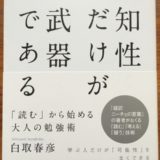おはようございます、一龍(@ichiryuu)です。
今日ご紹介するのは100歳で現役医師の髙橋幸枝先生が書かれた『100歳の精神科医が見つけた こころの匙加減』 。
現役の医師としての見地と、100年の人生経験から説かれる「匙加減」は、説得力とともに独特の味があります。
今回は 第3章 健康の匙加減 より、高齢者が気をつけなければならない健康に関する「匙加減」をご紹介します。
100歳の現役医師がすすめる健康の「匙加減」のポイント
★病は口からやってくる
健やかに生きていくことができるかどうかは「口」にかかっています。
なぜなら、口は食べ物を体内に取り込む入り口だからです。
具体的に言うと、気をつけて欲しい点は2つあります。
1つ目は「歯の手入れ」です。
これは若いうちから気をつけてください。
2つ目は「誤嚥性肺炎」です。
これは年齢を重ねてから心してください。
私は80代で、インプラントに挑戦しました。インプラントとは「人工歯根」と訳されます。虫歯などで歯の状態が悪くなった場合、その歯を抜いて、あごの骨に「ネジ」状のもの埋め込んで、そのネジを土台にして人工の歯を装着すると言う治療法です(もともと歯がないところに、インプラントを行うこともあります)。
「噛める」「噛めない」を気にしなくてよくなったため、ストレスがなくなり、「先生は最近丸くなってきた」と周囲に言われるようになりました。もちろん今でも、経過に何も問題はありません。インプラントのおかげでよく噛めるので、頭に刺激を与えることができ、脳の活性化にも役立っているようです。
2つ目は「誤嚥性肺炎」です。誤嚥性肺炎とは、細菌が唾液や胃液と一緒に肺に流れ込むことで起こる肺炎を言います。厚生労働省の人口動態統計(2014年)によると、高齢者の肺炎の6〜8割以上が誤嚥に関連しており、死亡原因ともなっています。年齢を重ねると誤嚥性肺炎が起こりやすくなるのには理由があります。反射作用が鈍くなるからです。だからお年寄りは、食べ物を食べたり飲んだりする時は気をつけるべきなのです。
ある意味、口は本当に災いの元なのです。
★脂肪は控えて肉も魚も楽しもう
たとえば、「高齢者は健康のために、肉食を控えるべきか否か」といった論争まで勃発しているそうですね。個人的には、お肉を健康のためにあえて控える必要はないと思います。たしかにお肉は脂肪分が多く、消化の負担にもなりやすいでしょうし、「控える」という姿勢は誤りではないかもしれません。でも、お肉にしか含まれていない希少な栄養素だって存在します。「何かをとりすぎる」ということと同じくらい、「何かを極端に制限する」という食事法には危険がひそんでいるかもしれませんよ。楽しくおいしいと思っていただくことが最もよい健康法だと思います。
★室温の「匙加減」は命にかかわる
わが家では、居間の目が届きやすいところに温湿度計を置いて、よく確認するようにしています。「快適に過ごせる室温は約29度、湿度は65%」と、自分なりの指標も持っています。今はデジタルタイプのものも含めて、さまざまな温湿度計が出回っているので、見やすいものをひとつは設置しておくことをお勧めします。また、夏場に熱中症にならないためには、常日頃から気温についてもっと鋭敏な感覚を養っておくことが大切です。例えば、家にいながらでも風通しを良くして「そよ風を感じる」という感覚を磨いておきたいものです。
★洋服選びが上手ければ、寿命も延びる
年齢を重ねると、洋服選びに頭を悩ませる局面が多くなります。「何と何を組み合わせたら、よく見えるかしら?」とワクワクする方向だけに頭を使うのであれば、なんと理想的なことでしょう。けれども、ある一定の年齢を超えると、ファッション性よりも「この装いで寒くはないか?」という条件を、真っ先に吟味しなければならなくなります。
若い人の真似をして、薄着のおしゃれをするなんて、”痩せ我慢”を通り越して、ナンセンスとも言えます。「洋服選びの際には、暖かさを優先させなさい。さもないと、あっという間に風邪を引きますよ」老婆心ながら、また1人の医師として、こう申し上げておきたいと思います。
★眠れないときは無理して寝なくていい
不眠はどんな世代にも見られる症状ですが、年令を重ねてからの不眠症のことを、専門用語で「老人性睡眠障害」と言います。「浅い眠りしか得られず、ときどきトイレに行きたくなって起きてしまう」という流れを一晩中繰り返すのが特徴です。
苦しい夜を過ごした翌朝は、「時間を無為に過ごしてしまった」という悔恨の情が湧いてくることもあるかもしれません。そこで大事なのは「もし眠れなかったとしても、翌日の朝も暗い気持ちで迎えない」ということです。「たとえ眠れなかった夜も、翌朝を明るい気持ちで迎えられればそれでいい」ととらえるようにしています。朝日を浴びて、気持ちを立て直していきましょう。
★投薬の「匙加減」は、主治医を使用するのが鉄則
私たち医師が処方した薬については、ぜひその用量と用法を守って、きちんと飲み続けてほしいと思います。これは精神科に限らず、医療全般について言えることで、ほかの多くの医師も皆そう考えられているはずです。ときどき「症状が軽くなったので、もう飲まないでよいと思った」などと、勝手に減薬、断薬してしまう患者さんがいます。その結果、予期せぬ症状が出る危険性も否めません。そして、もう一つお願いがあります。これは逆の事なのですが、「必要以上に薬をほしがらないでください」ということです。「せっかく受診したのに、何も薬はもらえないのですか」などと言う患者さんも時折いらっしゃいます。医師はさまざまな状況を想定して、あらゆる条件を計算して処方しています。医師が薬は不必要と判断した場合には、それなりの理由があるはずなのです。とくにご高齢の患者さんは「薬が多いと安心する」という方が多いです。「薬が多いと安心する」という気持ちは、私ももちろんわからなくはありません。「薬の種類が増えれば増えるほど、早く治る」そう感じる方も中にはいるかもしれませんね。ですが、人間の体というのはそれほど単純なものではないのです。かかりつけの主治医を信じて、薬と楽しくつき合っていきましょう。
感想
心の問題と高齢者問題。
この2つは現代日本にとって大きな課題ですよね。
著者の髙橋幸枝先生は100歳になる現役精神科医。
世の中に精神科医の方はたくさんおいでて、著書もたくさん出ていますが、やはり100歳でないと語れないことというのはあるものだと本書を読んで感じました。
今回は健康に関することだけに絞って紹介しましたが、健康というテーマだけでも100歳の経験からくる実感に医師としての知識も加わり、独特の説得力があります。
例えば「眠れない時は無理して寝なくてもいい」という言葉。
これ、僕のような数秒で寝付いてしまう快眠人間が言っても説得力ないでしょうし、若い精神科医が言っても同じですよね。
100歳の高橋先生に言われたら、「ああそうなんだ」と安心できます。
こういった、安心感をいただけるのは本書の魅力。
もちろん、本書からいただけるのは安心感だけではありません。
この先生、いくつになってもチャレンジ精神旺盛というところに勇気づけられます。
たとえば今回ピックアップした中にインプラント治療がありますが、これはかなり大掛かりな外科手術を伴うもの。
80歳でインプラントの手術を受けるというのはかなり思い切った決断だといえます。
おそらく僕だったら、「もう何年生きるかわからないし、入れ歯でいいや」となるでしょう。
しかし、それをするのは「噛める」ことへの一種の投資ですよね。
人間、いつ死ぬかはわからないもの。
寿命のことなど考えず、先々への投資というものは、年令に関係なくするべきなのだということも本書から学びました。
自分自身がこれから老いに向けて勉強になったのと同時に、年を取った両親に本書はプレゼントしようと思います。
いくつになっても人生に真剣に取り組んでいこう。
そんな気にさせてくれる一冊でした。
本書は飛鳥新社様から献本していただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに
第1章 生き方の匙加減
第2章 暮らしの匙加減
第3章 健康の匙加減
第4章 人づき合いの匙加減
第5章 やさしさの匙加減
おわりに
関連書籍