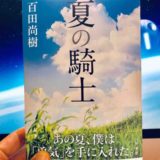おはようございます!
今日ご紹介する本は、
西田 二郎、 マキタスポーツ(著)『バカともつき合って』主婦の友社
です。
表紙からもタイトルからもわかるように、某本に便乗した(?)パロディ本に見えてしまい、後述しますが僕もとんでもない勘違いをしつつ読んでしまったこの本。
実は生きにくさを感じている人にとってとても勇気をもらえる生き方論の良書でした。
では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!
西田 二郎、 マキタスポーツ(著)『バカともつき合って』:読書メモ
★人の影響を受けまくれ
確固たる自分のオリジナリティーがあるものとして、それを人に示したいと思っていれば、それがプレッシャーになる。僕にしても、そういうプレッシャーのためにケッペキになってしまい、人を寄せ付けなくなった時期があった。
「自分がない」という言い回しがあり、批判的に使われることが多いといえるだろうが、自分がないのはべつに悪いことではない。
役者の仕事をするようになってからは特にそう思うようになった。役づくりという意味だけではなく。いろんなものを吸収してとり入れていくことによって自分を引き立たせられるということを肯定的にとらえるようになっている。
★身につけるべきは「編集力」
人の影響受けて自分のものにする、というのは、何もタレントに限った話ではなく、個人個人でも同じことだ。生まれついての自分を過信することなく、いろいろなものから影響を受け、それを自分なりに編み上げればいい。
つまり「編集」だ。
僕には本や雑誌づくりの経験はないが、テーマを決めて、原稿や写真を集め、届ける相手に向けて、より伝わりやすい表現を求め、見やすいレイアウトを組んでいく。
それ自体、自分なりのセンスが求められること。先人や先輩から吸収しながらも、ただ同じことをするわけではない。それでは編集をしていないことになる。そこに、自分なりのセンス、つまり方法論を織り込んでいく。これは何も、本や雑誌に限った話ではないはずだ。その人の生き方も、編集できると考えればいい。
編集してつくり上げた自分のを提示することで社会とつながっていく。本や雑誌が読者とつながるように、編集された自分もまた、そのセンスでつながるコミニケーションを読むことができるということだ。
★「いとおしいバカ」と「イヤなバカ」
バカを分類すれば、「いとおしいバカ」と「イヤなバカ」がいる。
立川談志さんは、状況判断ができない者がバカだと言っていたそうだ。それもそうかもしれない。とはいえ、そうしたことから生まれる迷惑さを上回るチャーミングさを持っている人も、一方でいるものだ。
バカと呼ばれる人がいないところではシリアスなコミニケーションしか成り立たなくても、バカと呼ばれる人がいれば、ぐるっと回ったコミニケーションがとれる場合もある。
無意識的にとはいえ、そんな役割を果たしてくれる人間をバカと呼んでいいものなのか・・・。たとえバカだと呼ぶのだとしても、そばにいてくれてもイヤではないタイプのバカだといえそうだ。
僕の感覚でいえば、なんでも知ったかぶりをしていて、自分がバカだと思っていない人間がいちばんバカ度が高い気がする。そういう人間が、さも正義であるようにふるまっていれば、ものすごく君が悪い。
★自分でなく脳みそをほめる
その頃思いついたのが、自分の脳みそを褒めるというやり方でした。
「オレ、あの人のこと、好きやわあ」といったことを脳みそに言って聞かせるだけでなく、いろいろなタイミングで脳みそに話しかけ、脳みそを褒めてあげるようにしました。
脳は再現の器官。常日頃から言い聞かせていれば、言葉を現実化してくれます。自分の中にある情報を整理して、必要な形に最適化することもできるはずです。
「アイディアが降ってくる」という言い方をする人がいますが、それも結局脳がそう働いてくれたということ。
空から降ってきたようなアイディアに助けられたときには「オレってすごい」と自分を誇るのではなく、脳みそに対して「ありがとう」とお礼したらええ。
そうやっていてこそ、脳が次を出してくれるからです。
★売り買いされるのは能力ではなく「可能性」
そもそも、人生の中で売るべきなのは「可能性」であり、能力を売るべきではないはずです。
なぜなら、可能性の先には継続があるのに、能力の先には結果しかないからです。例外的なケースを除けば、結果がよければ続けられても、結果が悪ければ次は無い。
能力よりも可能性を感じてもらえていたなら違ってきます。可能性が提示できていれば、結果が出せなくても、次を期待してもらうことができるからです。
人は可能性を感じた時のみ、相手の行動を許します。
★社内外で御用聞きができればサラリーマンは2.0に
僕は部局を超えたポジションになっていく発想が大切だと思います。
自分の所属する部や課だけに縛られず、どこの課にも顔出していき、「なんかない? あったらやるで」と御用聞きをする。
制作にいた頃などは特に閉じこもりがちになりやすかったので、営業や編成に出向いたりしながら、社内でネタを拾って回っていました。そうしていると、「次郎さん、こんなこと知ってますか?」と教わったりして、新たな発見を得られることもありました。
悪びれず、恥ずかしがらず「なんかない?」と聞いて回る。
こうした継続が、サラリーマンを自由にする基盤になっていくんだと思うんです。
★自分のプロフィールを作る
これまでの自分が何をやってきたかという実績をテキスト化していない人も多いと思います。でも、その作業もしたほうがええと思います。
実際に文章として書き起こしておかなくても、「自分が何をやってきて、どんな価値を持っているか」を整理しておき、人に伝えられるようにしておくということを意識する。
自分のプロフィールをつくって眺めていれば、”未来のプロフィール”にこんなことを書き込みたい、という気持ちが生まれるものです。
それが次のアクションを呼んでくれます。脳が、その未来に向かって動き始めます。
★「バカな自分」に人を巻き込む
「バカなこと」と思われるようなことにも、自分にとっては大事なことやったら、どんどん人を巻き込んだらええんです。
誰とでもつき合、バカな自分にもつき合ってもらう。
人と交わる扉を閉ざしてしまえば、バカがバカのままじゃないですか。
そんなもったいないことあります? ひとりの可能性が、単なるバカで終わってしまうなんて。
この本をここまで読んでいただいたみなさんには、自分の中の「バカ」をどんどん解放してほしいと願っています。
西田 二郎、 マキタスポーツ(著)『バカともつき合って』:感想
◆『アホともつきあってぇなぁ』だよね
この本の感想を書く前に、まず一つ僕のバカぶりを告白させてください。
実は僕はこの本の著者をお二人とも存じ上げなくて、特にマキタスポーツさんに関しては、「マキタスポーツ」というスポーツショップの店主さんだと勝手に勘違いしていました。
で、僕と同世代のどこかのオッサーン二人がバカ論を放談する本だとばっかり思い込んで読み進めていて、「なんかおかしい、なんかへんだぞ」と思いながら半分くらいまで読み進めてしまいました。
テレビは見ないし、芸能界に疎いとはいえ、「早く気付けよ!」って感じですよね。
僕もバカ仲間ということでご容赦ください。
さて、仕切り直して感想などを。
まずね、タイトルに違和感があるんです。
この本は、西野亮廣さんと堀江貴文さんの『バカとつき合うな』に公式に便乗した本なので『バカともつき合って』というタイトルになっています。
で、この『バカとつき合うな』で書かれている「バカ」とは僕も本当にもう付き合いたくなくて、すごく共感したんですね。
一応、高校教師を26年していましたから、「いいかげんにしてくれよ!」という同僚のバカ教師もたくさんいました。
生徒と問題起こしておいて、その尻拭いを担任の僕に全部丸投げするバカ教師とか最悪でしたよ(管理職にもこういうのがいたからね)。
人の時間を奪って平気な人とか、仕事から逃げる人とか、そういった「バカ」には僕はすごく厳しくて、容赦しません。
でもね、この『バカともつき合って』で論じられている「バカ」はそういう人たちとは違うんですよ。
言わば「愛すべきバカ」なんですね。
なので、これは関西文化圏の人しかわからないと思いますが、この本は『バカともつき合って』ではなくて、『アホともつきあってぇなぁ』がしっくり来ます。
関西では「バカ」と「アホ」のニュアンスが、関東と多分逆で、「変なことするし、失敗も多いけど、なんかあいつは憎めないよな」という存在は「アホ」。
だから「お前アホちゃうん」という言葉には愛が含まれています。
逆に標準語のアクセントで「バーカ」とか言われると関西人はカチンと来ます。
そこに愛を感じないんですね。
◆「バカ(アホ)」は人生を生きる術であり、世の中を変える鍵
で、本書で言うところの「バカ(アホ)」ですが、僕はこの「バカ」こそがこれからの時代を生きていく上での鍵となると思っています。
大げさに聞こえるかもしれないけど、真面目に言ってます。
人生100年時代、死ぬ間際に「ああ、俺の人生楽しかったな」って思いたいじゃないですか。
歴史に残るような記録や成果を残せなくても、「人生楽しかったな」と思えたら生まれてきたかいがあったというもの。
逆に一番イヤなのは、「あのときああしとけばよかった、あれをやっておけばよかった」なんて後悔や未練タラタラで死んでいく人生。
他人からどう思われたって構わない、自分のしたいことを、迷惑なんて気にせずまわりも巻き込んでやっていく。
この生き方が一番幸せなんだと思います。
ちなみにスティーブ・ジョブズはスタンフォード大学の卒業式のスピーチで
「Stay hungry, Stay foolish」(ハングリーであれ、バカであれ)
と言いました。
閉塞感を突破し、世界に新しい風を吹き込むのは、ずば抜けた「バカ」なのだと思います。
僕も「バカ(アホ)」で有り続けたいと思います。
◆西田二郎さんの母の言葉
最後に、これはぜひ本書で読んでほしいのでこの記事には記載しませんが、本書終盤に登場する西田二郎さんのお母様の言葉がとにかく素晴らしい。
この言葉を読んだとき、背中に電気が走りました。
もうここを読めただけで、本書は元を取れます(なら、お二人が書いた部分は何やったんやとツッコまれそうですが)。
僕も含めて、バカは自分がバカなことを知っています(どうしようもないバカは一生気づかないけど)。
だから常に不安でもあるんですね、「オレ、だいじょうぶかな?」って。
たぶん、この言葉を読むことで、心が楽になる人、開放される人がたくさんいるんじゃないかな。
大丈夫、自由に生きよう!
この本が勇気をくれます。
本書はセンジュ出版様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに 西田二郎+マキタスポーツ
1章 マキタスポーツ
2章 西田二郎
3章 バカともつき合って!
関連書籍
西田二郎さんの著書
マキタスポーツさんの著書