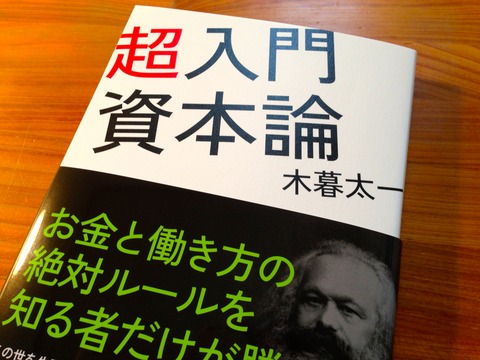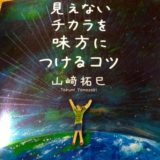おはようございます、一龍です。
今日は、木暮太一さんがあのマルクスの『資本論』を使ってこれからの働き方を紐解いた本をご紹介します。
右とか左とか思想的なものは置いといて、とにかく一読。
給与に関して、かなり衝撃を受ける内容となっています。
はじめに
『資本論』というと、「レフトの方のバイブル」としてのイメージが強すぎですし、20世紀に社会主義が失敗してしまった今となっては「何を今更?」とも感じてしまいます。
しかし、著者によると資本主義の原則、ルールを学ぶのにこれほど良いテキストはないのだとか。
なぜなら『資本論』は資本主義経済の本質を研究している本だからだそうです。
本書では『資本論』をもとに、われわれの給与の決まり方を説明するとともに、そこから資本主義社会でどう生きるべきかを説いています。
まずはポイントを御覧下さい。
『資本論』から読み解く給与と働き方のポイント
★「価値」、「使用価値」、「社会平均」
1.商品には、「価値」と「使用価値」がある
「価値」・・・「労力の大きさ」「それをつくるのにどれだけ手間がかかったか」
「使用価値」・・・「使うメリット」「それを使ったらメリットがある、満足する、有意義である」
2.商品価値の大きさは「社会一般的にかかる平均時間・平均労力」で決まる
その商品の価値は「その社会で平均的に考えて、必要な手間の量、時間の量」で決まる。
★「頑張っても評価されない・・・」と嘆くのは筋違い
使用価値が上がれば、「その商品がほしい!」と思う人が増えます。一般の商品で考えれば、使用価値があれば、消費者に選んでもらえます。そして、継続して買ってもらえます。
これを労働力で考えると、「労働の使用価値があれば(その人が優秀で、企業に利益をもたらせば)、企業に選んでもらえる、継続して雇ってもらえる」となるのです。
お気づきでしょうか?
労働者として優秀になり、企業に利益をもたらすことで得られるのは「雇い続けてもらえること」なのです。給料が上がることではありません。2倍の成果が出せるようになっても、給料は2倍にはなりません(先ほどの話の通り、1.2倍くらいにはなるかもしれませんが)。
そういうものなのです。それが資本主義経済における給料のルールなのです。
★給料を高くするには
給料は、労働者が出した成果で決まっているのではなく、労働者の価値、つまり「その労働者が明日も仕事をするために必要なコスト」で決まっています。
この「必要なコスト」には、食事・住居などの体力を回復・維持させるために必要なお金だけでなく、その仕事をするために必要な知識・経験・技術を備えるためにかかるコストも含まれます。
医者や弁護士など、専門的な知識や長年の経験が必要な仕事は、そのために必要な知力を身につけるのに膨大なコストと労力がかかり、そのため医者や弁護士の給料は高い、という話をしました。
そして、現代の厚生労働省の統計データからも、マルクスの理論が当てはまっていることを確認しました。
つまり、給料を高くするためには、「労働力の生産コスト」を引き上げることがポイントなのです。
★給料は「必要経費分のみ」
逆に考えると、労働者は「明日働くために必要な分」しかもらっていない、ということがわかります。
「ひと月に数回は飲みに行って気晴らしをしないと、やってられない」と考えられていたとしたら、その飲み代も「必要経費」として給料に上乗せして支給されます。
ただ、これも「精神衛生を守るための必要経費」なのです。必要だからくれるわけであって、決して労働者が「頑張ったから」でも「成果を出したから」くれるわけでもありません。
ぼくらの給料は、このように必要経費方式で決まっているのです。
だから、「サラリーマンはいつまでたってもしんどい」のです。
★資本主義のジレンマ
業務が効率化され、商品が大量生産される、まさにその過程で、機械化が進みます。機械化が進めば、必要な労働力が減り、労働力の価値も下がります。
つまり、給料を受け取れる人の数が減っていくのです。
同時に、もらえたとしても、その給料の金額は成熟社会では減少していきます。というのは、社会が進歩し、「労働者が生活するのに必要な経費」が減っていけば、労働力の価値(=給料)も減るからです。
これはすなわち、企業の生産力はどんどん増え、労働者が受け取る給料総額は、どんどん減っていくということなんですね。世の中に提案される商品が増える一方で、それを買う国民(=労働者)の購買力は減っていくことを表しています。
企業がもっと利益を増やそうとする行為自体が、やがては企業が利益を出せなくなる状況を作り出してしまうということなのです。
これは大きな矛盾です。資本主義のジレンマです。
★「昇給に依存しない働き方」をしよう
労働者としてのぼくらは、「昇給に依存しない生き方」を目指すべきなのです。
そして、「昇給」の代わりに、「自分の必要経費を下げる働き方」を目指すべきなのです。<中略>
仕事をするときに、かかるコストが社会平均よりも低い仕事を選ぶのです。<中略>
もし、「自分はその仕事をしても、そんなに疲れないから疲労回復はそんなに必要ない」「そんなにストレスを感じないから、気晴らし代はそんなに必要ない」と思っていたらどうでしょうか?
給料は世の中の平均で決まりますので、仮に「自分はそんなにコストがかからない」と考えていても、社会平均分もらえます。
そしてその差額は、自分の利益になるのです。
★企業に依存しない「フリーランス・マインド」
フリーランス・マインドで働くとは、文字通り「フリーランスのつもりで働く」ということです。それはつまり、サラリーマンの評価体制から抜け出すということです。
そして、マルクスが説いた商品の原則に立ち返り、労働力を「商品」として見直すことです。<中略>
フリーランス・マインドで働くということは、実際にフリーランスになるということに限らず、「労働力の価値ではなく、労働力の使用価値で評価を受けること。その覚悟を持つこと」です。<中略>
また、望んでも、望まなくても、雇用の流動化は進みます。自分が終身雇用を望んでいても、もはや難しいのです。
だとしたら、労働者としての僕らに必要なのは、今の職場がなくなったときに、次の仕事をすぐに見つけることです。
今いる企業に(過度に)依存せず、自分の能力を使って社会を渡り歩くことです。要するに、労働力の「使用価値」を評価してもらい、使用価値に基づいて給料をもらうべきなのです。
★コモディティ化しないための3つの法則
1.変化耐性をつける
ほかにお金を稼げる手段を持ち、フリーランス・マインドでいつでも動けるようにしておく。
2.能力を汎用化させる
自分の仕事を目の前の作業内容から切り離して、どう役立っているのかを考え、他の業界でも応用できるスキルに変える。
3.USPをつくる
相手にとってのメリットがあり、ライバルが少なく、時間とコストをかけて積み上げられる、マネされにくいウリをつくる。
感想
◆『資本論』から分かる僕らの値段
いかがでしょうか?
本書では、『資本論』の3つのエッセンス
1.「価値」と「使用価値」
2.「剰余価値」
3.「剰余価値」が減っていくこと
をもとに、給与の決まり方、資本主義の抱えるジレンマを見事に解説してくれています。
そしてその内容がかなり衝撃的。
たとえば資本主義の本質とジレンマ。
どんなに素晴らしいアイデアであろうと、画期的な新商品を出そうと、そしてそれが大ヒットしたとしても、資本主義経済の中ではそれがすぐに陳腐化してしまう。
要するに資本主義経済とは、それ自体がエンドレスなラットレースだということ。
その車輪の中で「いつかきっと・・・」と夢見ながら我々は必死に走っているけれど、当然その「いつか」はくることはなく、生活が楽になることはない。
幸せになるために、豊かになるために私たちは働いているのに、資本主義経済の本質とはそういうものだったんですね。
◆僕らの給料は”必要経費”
さらに、そのラットのように走り続けなければならない僕らの給与は
給料を決めているのは、労働力の生産コスト(=知識・経験の取得や体力の回復・維持にかかるコストの合計)である。
ということで決まっていると。
要するに”維持費”なんですね。
食って寝て、明日も会社に出て来れるだけの最低限の維持費。
だから、たとえ会社に莫大な利益をもたらしたとしても、給与が何倍にもなるということはまずありえない。
高度経済成長期には数年で給料が倍になったこともありましたが、そんなことはもう起こらないのです。
ちょうど高度経済成長期の給与がどんどん上がる時期を体験した私のオヤジは、「大変でも仕事を大事にしろ。続けていたらきっといい事があるぞ」と口グセのように私に言いますが、そんなことを信じていたら、きっと死ぬときに後悔することになるでしょう。
真面目に働いているだけで豊かになれた時代は、もう終わったのです。
◆まずは自分の労働者としての「価値」を見極めよう
では、企業に雇われる労働者は、資本主義の構造上豊かになれないのなら、我々はどう生きるべきなのでしょう。
企業の経営改善ではよく「固定費を下げる」というのが基本でありますよね。
個人の労働者も同じで
「自分にとってコストがかからない仕事を選ぶ」
という方法を著者は考えてみることを薦めています。
この考えの行き着く先は、
「好きなことを仕事にする」
ということでしょう。
他人から見れば大変な仕事でも、自分にとっては楽しい。
全然苦にならない。
そういう仕事と出会えたら、”維持費”が低く抑えられるので得するわけです。
しかし、現実的にこれはかなりレアなケース。
となると、残された道は、自分自身で”商品価値”を上げていくこと。
そしてこれはなにも、フリーの特権ではありません。
勤めながらトレーニングができるのです。
企業で働きながら、「フリーランスマインド」を持って自分自身の商品価値を高めていく。
良くも悪くも安定した給料をもらえる立場を確保しつつ、いつでもフリーになれる準備をしていく。
言葉は悪いけど
「社畜の仮面をかぶって、こっそり爪を研ぐ」
といった、したたかな生きかたをサラリーマンはしていくべき時代なのでしょう。
そのためには、まずは自分の労働者としての価値を見極めるところからスタートです。
本書はダイヤモンド社、市川様から献本していただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに
第1章 なぜペットボトルのジュースは150円なのか?<価値と使用価値1>
第2章 年収1000万円でも生活がカツカツになる本当の理由<価値と使用価値2>
第3章 ぼくらは知らぬ間に給料以上働かされている<剰余価値>
第4章 なぜパソコンの値段は下がり続けるのか?<剰余価値の減少>
第5章 合格しないと生き残れない「命がけのテスト」
第6章 勝者だけが知っている生き残るためのルール
第7章 コモディティ化せずにこの世を生き抜く3つの方法
おわりに
関連書籍
同著者のこちらの本もオススメ
Amazonの内容紹介より
ベストセラーになった第1弾『カイジ「命より重い! 」お金の話』と、同シリーズの第2弾『カイジ「勝つべくして勝つ! 」働き方の話』に続く第3弾、満を持して刊行です!
「“お金”と“働き方”と“生き方”は、三位一体である」とシリーズのはじめから主張してきた著者が、本書の中で最後に提示する残酷な世界を生き抜くルールとは何か?
「未来は、ぼくらの手の中」――この印象的な言葉からはじまっている大人気漫画『カイジ』を、今回は「生き方の教科書」として読み解きました。