“不機嫌な職場”が取りざたされる昨今、職場の「組織感情」に心を砕いている経営者も多いでしょう。
実際新聞などを見ていると、一番働き盛りの30代後半から40代半ばまでのいわゆる“ミドル”がストレスなどからくる心の病に一番多くかかっています。
ワタクシも職場を見ているとこれは実感するところ。
今回はそんな職場環境や社員の健康に苦慮している経営者や“ミドル”の方に読んでいただきたい1冊を紹介します。
【目次】
プロローグ 組織感情を何とかしたい!
第1章 ご機嫌な職場をつくる第6の経営資源
第2章 組織感情を分析する方法
第3章 自己の振り返りと相互コーチングの重要性
第4章 公開! リフレクション・ラウンドテーブルのノウハウ
第5章 組織を元気にするための処方箋
エピローグ Will=「思い」から始まる幸せな組織
簡易版 組織感情診断シート付
【ポイント&レバレッジメモ】
◇「人間らしさへの回帰」
バブル崩壊以来、日本のビジネスパーソンは情緒的判断を排し、論理的・理性的に判断することを志向してきた。いわゆる左脳を育ててきたのだ。山積する課題解決のために、ロジカルシンキングや戦略的思考などを必死に学んできた。このこと自体は悪いことではない。ビジネスのおいて論理的判断にたけることは望ましいことである。問題は、それに反比例するかのように、右脳的な能力ともいうべき直観力や発想力、感じる力が弱まってしまったことだ。
◇「活性化した組織」・・・「組織本来の目的を組織成員が共有し、主体的・自発的に協働しながら達成しようとしている状態」
◇「反応型組織感情」・・・特定の刺激(目標など)に対して、その組織固有の感情が励起されるようなものの感じ方が共有されるとき ⇔ 「ベース型組織感情」・・・特定の刺激がなくても、固有の感情が組織に共有されている
◇「組織感情」は、個々人の感情が連鎖し、組織全体の感情として広がってしまった状態を指している。 ⇒ 「組織の気分」・・・組織全体に感情フィルターがかかってしまい、組織全体の反応を歪めてしまうこともある。小さな組織であれば、それこそ一個人の感情の起伏がそのまま組織の気分となり、個々人の感情に影響を与えてしまうこともある。
◇「フロー体験」・・・実践の中で重要な節目となるイベントのこと(ミハイ・チクセントミハイ) ⇒ 頭の中が真っ白になるほど何かに集中した没入体験をすることが極めて重要で、そのフロー体験の量と質によって、その人がどれだけ育つかが決まる。
◇フロー体験をいくら積み上げてもそれだけではダメで、どこかで一度立ち止まって、自己を振り返る、すなわち内省(リフレクション)することが大事 ⇒ 右脳的に、つまりは本能的に、感覚的に、空間認識的に没入した体験について左脳的に、つまりは論理的に、言語的に振り返る。この繰り返しこそが重要。
◇「マネジャーの仕事」3カテゴリー10項目
●対人関係
・組織の代表として振る舞う
・メンバーを動機付けて雰囲気を作る
・外部とのつなぎ役を務める
●情報処理
・内外の情報を察知する
・情報を組織内に周知伝達する
・情報を組織の外に発表する
●意思決定
・創造的案件の意思決定をする=起業家的な役割
・対応型案件の意思決定をする=困難な状況を切り拓く
・資源の配分を行う
・交渉役を担う
★リフレクション・ラウンドテーブル(RRT)
◇前提となる三つのポイントと5段階のマインドセット
三つのポイント
第1のポイントは、自分や他人の経験について、旺盛な好奇心と興味をもつこと
第2のポイントは、内省
第3のポイントは、鵜呑みにすること無く、冷静な目をもつこと
5段階のマインドセット
第1 内省
第2 行動
第3 分析
第4 協働
第5 世界観
◇マネジャー(ビジネスリーダー)としてのマインドセット
①自分を知る
②組織を知る
③視野を広げる
④人を知る
⑤変革を進める
◇「おもしろがり力」・・・おもしろがれる人間は、そのプログラムなどが意図されていなかった応用の仕方をして成果を出すことができる。
「質問力」・・・いい質問というのは、相手や場に対して気づきを促す効果がある。
◇重要なことは、ディスカッションを通して、自分たちの経験を引っ張りだしてくることだ。大事なのはテキストの中身でなく、身の回りに起こったことをいかに正しく解決できるか
◇「マネジメント・ハプニング」(マネハプ)・・・毎回のセッションの前に15分程度行う。ひとり2分程度、実際のマネジメントの現場で起こった出来事、洞察、内省、経験を発表する。
◇人の話を聞く傾聴の姿勢と、質問力は非常に重要な成長のエンジン。 ⇒ 「積極的傾聴」とは相手の姿勢、表情、視線、しぐさを漏らすことなく注視し、話し手が語る言葉だけでなく、その裏側にある暗示やヒント、ひそかな誘惑や攻撃などを探りながら聴く。
◇傾聴と介入は、マネジャーにとって非常に重要な役割。マネジャーは優秀な聞き役に回らなければいけない。
★組織を元気にするための処方箋
◇リーダーシップ論では、大きなビジョンを掲げるリーダーに焦点を当てる。しかし重要なのは、ビジョンというものは与えられるものではなく、自ら共感するものであるということだ。
◇実は、動機づけは個人の中だけでおこるものではない。むしろ、周囲との関連性の中から生まれてくることが多いのだ。お互いが関心を持ち合い、やっていることにちょっとしたフィードバックを加えることで、感情の連鎖が生まれ、それが一人一人の感情に影響を与えていく。つまり、組織感情が個々人のやる気に大きく影響を与えるのだ。
◇やる気はそもそも感情の問題だ。論理思考で夢やロマンを感じる人はいない。感情が夢を語り、使命感に涙する。外発的動機付けには合理的な理性が働くかもしれないが、内発的動機付けは感情そのものだ。
【感想など】
本書は帯にあるように
「不機嫌な職場」を変えたい!「壊れたミドル」を再生したい!
「組織感情」を活性化することで第6の経営資源を生かしたい!
そのために著者の野田稔氏が開発したメソッドであるリフレクション・ラウンドテーブル(RRT)を解説した本である。
RRTの詳しい内容や実践方法は本書を読んでいただくとして、
ここでは簡単に触れるだけにしますが、
ワタクシも職場で同僚や先輩後輩、他部署の方たちとコミュニケーションを密にし情報交換をするセッションをいくつか経験したことがありますし、研修やセミナーに出されたこともあります。
が、今回読ませていただいたRRTの特徴はこれまでのものとはちょっと違って
内省と共有、ならびに対話を通した他者からの気づきを重視
している点かと。
つまり、RRTの場というのは基本的に
指示に従うのではなく、マネジャーとして、どうすべきか、自分に問い続ける場
と言えるのではないでしょうか。
特にワタクシが「これはいいなぁ」と思ったのが「マネジメント・ハプニング」
次のRRTが開かれるまでの1週間で、実際のマネジメントの現場で起こった出来事を題材に、自分の洞察、内省、経験を発表する。
そしてそれに対して参加者が積極的に“介入”し、「すごい!」と称賛したり、同じような経験を披露したりするというもの。
そこには非難や評価というものが存在しないのでミドルにとってはセッション自体が心理療法のようになっているのですね。
人に知ってもらうとか認めてもらうというのは人間にとって根源的な欲求だと思うのですが、これが安心してできる環境が今の職場環境、ビジネスの場にはあまり存在していないように思えます。
ワタクシこの部分を読んでいて思ったことがあったのですが、おなじ意見が本書の中に研修者の意見として出てきます。
それは、
昔は同期入社が多かったし、課長ぐらいまではなる人間が多かった。飲み会も多かった。横の絆があった。しかし今ではそれがない。同期入社も少ないし、中途入社も多い。ランク付けをして、 成果を問う社会だから、横のつながりは希薄だ。若いうちはまだいいが、マネジャークラスになると、一緒に何かをするという機会は非常に少なくなる。
というもの。
確かにそうですよね。
特に職場がRRTのようなセッションを用意しなくても飲みに行ってパーッと・・・っていうパターンで人間関係もストレスもうまくいっていたような気がするのですが、
いつの間にか余裕がなくなってますね。飲み会も減ったなぁ(寂しい)
それに、ワタクシも年齢的にはミドルですので若手を飲みにつれていってやりたいのですが、今の若手って飲みにいくの好きじゃないみたいで・・・。
仕事が終わったらさっさと家に帰りたいのだとか(これってどうよ?日本はこれでいいのか?)
「飲ミニケーション」ってとっても大切なものだったのではないかと今更ながら思ってしまう。
最後に一つワタクシ的にやってみたいと思ったのが、「自分史の演習」
内省ということで己を知るのにとても良い方法だと思いました。
そして、自分の成功法則を知るのにも。
といっても成功経験が少ないのですが・・・(頑張れ自分!)
いずれにしても、
“不機嫌な職場”が取りざたされる昨今。RRTはなかなか良いのではないでしょうか。
職場の組織感情が心配な経営者の方、ぜひお読みください。
御礼
SoftBank Creativeの入山真一様を通して、著者の野田 稔様より献本していただきました。
学びの機会を与えていただき感謝しております。
【関連書籍】
【管理人の独り言】
日曜日に近所のTSUTAYAに行ってきました。
お目当ては「ビジネス書有名ブロガーが目利き!」というフェアで、
有名書評ブロガー6人がそれぞれ5冊オススメ本を紹介するというもの。
TSUTAYA全店で開催しているわけではないということだったので「こんな田舎じゃやってないだろう」と期待せずに近所のTSUTAYAに行ってみたら・・・・
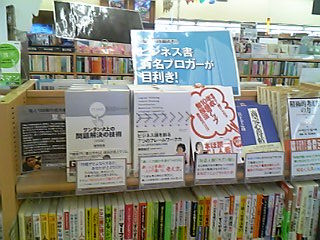
一棚だけでこじんまりとやってました。
この日はワタクシもファンの聖幸さんのお薦め本5冊が並んでいましが、
聖幸さん、なかなか渋いところを突いてきますね。
ん~、勝間さんの本以外の3冊は読んでいません・・・
いつかワタクシの棚ができるよう頑張ろっと!

