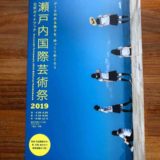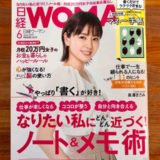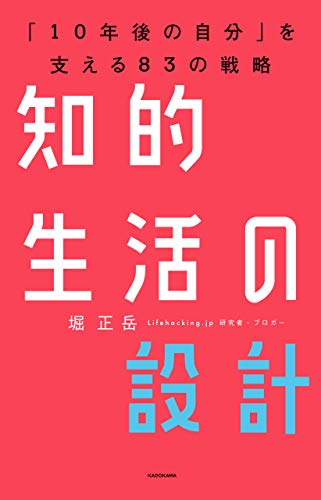
こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。
今日ご紹介するのは、堀正岳(著)『知的生活の設計 「10年後の自分」を支える83の戦略』です。
先日紹介した堀正岳さんの『ライフハック大全』が「5分で人生を変える」テクニック集であったのに対して、本書は「10年後を目指して今できること」、つまり中長期的な「知的生活」の「設計」を中心にまとめらています。
情報の収集方法から、書斎などの環境のことなど多岐にわたる内容ですが、今回は情報発信の場所としてのブログやSNSに関して書かれている部分を中心に紹介したいと思います。
では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!
『知的生活の設計』読書メモ
★知的生活を設計するための5つのポイント
(1)自分の「積み上げ」を設計する
1日たった15分の活動でも10年で考えれば約920時間の蓄積になりますし、週に1度しかできないことであっても10年で考えれば520回の実践になっています。
なんとなく行っていた趣味や好きな活動を、単なる一過性の知的消費ではなく、3年、5年、10年といったスケールで蓄積するためのチャンスと捉えることで、今日の楽しさが未来につながる可能性について考えてみましょう。
(2)パーソナルスペースを設計する
知的生活の積み上げを行うためのプラットフォームとして重要なのが、書斎のようなパーソナルスペースです。
安心して知的生活を営める現実のスペースと、実際の本棚であれ、クラウド上のデータストレージであれ、情報のアーカイブを許容する場所があれば事足りる場合もあります。
自分の生活と資金に合わせて、こうした パーソナルスペースを長い目でみて設計し、成長させてゆくという視点 が必要です。
発信の場所を設計する
あなたの知的生活から生まれた新しい情報を、どこに、どのような形で発信するのかを設計する必要があります。
発信をする人のもとには、さらに良質な情報が集まる傾向があります。蓄積と発信、インプットとアウトプットのバランスを考えることは、より豊かな知的生活を楽しむ鍵になります。
(4)知的ファイナンスを設計する
収入を得るための知的生活ではなく、自分の知的生活が自らを助けるような、長い目でみて維持しやすい経済的な視点もどこかにもっておくとよいでしょう。
(5)小さなライフワークを作る
ライフワークは一つである必要はありません。私が「国王は死んだ!」の使用例を集めているように、心の琴線に触れた情報を、感じた違和感を、長い目で集め続ける小さなライフワークをたくさんもちましょう。
そうしたライフワークのすべてが大きな結果を生み出すとは限りませんが、たとえ一つでも10年の積み上げが実を結ぶことがあるなら、それが結果的にあなたの人生の大きなライフワークとして残るかもしれません。
★情報発信で知的生活は完成する
一つは、発信によって蓄積した情報が整理されるというメリットです。情報を蓄積し、様々なつながりに気づいていとしても、それを実際に誰かに説明するとなるとそれなりの根拠や実例をまとめる必要があります。そこでようやく、自分の集めていた情報の意味に気づいたり、どのようにして説明すれば自分にも、他人からも納得が得られるのかが判明したりします。 二つ目に、発信を行うことによってさらに情報が集まってくる傾向があるという点です。ブログの記事を書けば、それに対する反応があります。SNSで発言すれば、ときには反論がやってくることもあるでしょう。引いた立場から見るならば、それは自分が発信した情報に対する答え合わせや、偏りをチェックするための試験になるのです。
★なにを発信するのか
発見を紹介する
本を読んだ感想、ウェブで見つけた面白い話題、話題のニュースなど、自分にとって面白いと感じた内容をそのまま紹介するだけでも立派な発信になります。
しかしここでただ話題を右から左に受け渡すだけでは、新しい情報はなにも生み出されていないことになってしまいます。そこで、ほんの少しでいいので、自分がその情報に対してどのように感じたか、過去の経験からどんな関連性を見出したかといったプラスアルファをつけ加えます。
立てた予想をその理由とともに述べるのなら、個性的な発信になるのです。
情報で人をつなぐバブになる
ソーシャル・ウェブのエキスパートであるポール・アダムス氏は『ウェブはグループで進化する』(日経BP社)のなかで、情報はインターネットのなかで均一に伝わってゆくのではなく、あるクラスタとクラスタをつなぐ「ハブ」のような人材を通してジャンプすることを指摘しています。
こうしたハブ人材はなにも特別な人ではありません。あるクラスタではよく知られている情報が、別のクラスタではまったく知られていないため、それをつなぐ発信をするだけでも価値が生まれるのです。
完成に向かうプロセスを発信する
完成したなにかがなくても、そこに向かうプロセスを発信することもできます。
★知的生活の発信先としてブログが最適な理由
知的生活の発信という視点で考えると、ブログがもっている最大のメリットは日々の発信というフロー情報が、記事がゆっくりと蓄積してゆくことによって自然にストック情報に変わってゆくところです。
年に104本の記事が、3年続ければ312本、10年続ければ1040本というデータベースに匹敵する情報の網目になります。こうなれば、ブログは価値の高いストック情報に変貌します。しかも、日々に追加しているのは、その日の1本のワインについてであって、作業は今日も10年先も変わりません。
同じことは、書評ブログであれ、旅ブログであれ、写真や動画やマルチメディアを埋め込んだブログでもいえます。 日々の小さい発信がやがて知的生活の大伽藍に成長する のが、ブログが知的生活の発信プラットフォームとしてもっている最大の魅力といっていいでしょう。
★ブログはあらゆるメディアをつなぐのりの役割をもつ
ブログは長い歴史をもっているからこそ消し去り難い、技術的な優位性ももっています。特定のアプリに依存せずにブラウザがあればパソコンでもスマートフォンでも閲覧可能ですし、動画も、音声も、ソーシャルメディアの投稿も埋め込むことが可能です。
活字を読むことが人間の情報取得の手段である限りブログは存続し続けると予想できます。
また、ブログは蓄積した情報を簡単に検索できることも重要な点です。それは人間にとってはカテゴリやタグをたどって話題を探しやすいということでもありますし、機械にとってはGoogleのようにブログ内の情報をインデックスしやすいということでもあります。
更新の簡易さや維持の容易さもあわせて考えると、知的生活の発信先としてブログは自然な選択となるのです。
★いまブログを始めるなら気をつけるべき点
(1)せめて一つのニッチはもっておく
単にグルメブログや、旅ブログといったテーマならば、すでに無数のブログが存在します。あなた自身の発信がいかに個性的で優れていたとしても、読者からみてすぐにその違いはわかりづらいでしょう。
そこで、ブログのテーマとしてせめてなにか一つは“ニッチ”なものを考えておくことによって、他と差別化しやすいようにするのが得策です。たとえば名言を紹介するサイトは多いですが、私が集めているような偽引用句を紹介するものはなかなかありません。情報を多く集めているからこそ切り込むことができるニッチがあれば、大きな武器になるでしょう。
(2)見た目の違いにも気を使う
ありきたりな日記ブログのデザインやデフォルトのテンプレートを使用するのもよいですが、ブログのテーマ選び同様、読者からみて違いを即座に認識できないのはもったいないことになります。
せめてブログの名前やテーマカラーはデフォルトから特色あるものを選び、読者にとって印象に残りやすいようにしておきましょう。同じ理由から、ブログを独自ドメインで運営してURLを独特にしておくこともおすすめします。
(3)専門家であるような口調を心がける
もっていない知識や経験を詐称するのはいけませんが、読者はあなたが自信なさげに弁解しながら書く記事を読みたいわけではありません。自分の知識の限界を素直に認めつつも、その分野の専門家であるような口調で書きましょう。
誠意をもって調べ、間違いを訂正し、さらに記事を書き続けるならば、口調のなかで先取りした矜恃は、やがて本物となって身につくはずです。
(4)カテゴリ分けとタグづけは入念に行う
ブログがストック情報として機能するためには、日々の蓄積がたどれるようになっていることが重要です。近年、Googleの検索にはノイズが多く混じるようになり、以前ほどロングテールの内容を探しやすくはなっていません。ブログの書き手自身が自分の情報をある程度組織化することが重要です。
せめて、主だった話題のカテゴリと、カテゴリを横断した索引としてのタグを記事に設定することによって、ブログの検索性を高めておきましょう。それはやがて自分自身が情報を見返すためでもあります。
★知的発信に向いている、ゆっくりとフォロワーを増やす戦略
(1)一貫性のある、気長な発信
あるテーマについて情報発信をすると決めたならば、あなたをフォローする人にとってそれがわかりやすいように、一貫性のある投稿を心がける必要があります。
発信は一度にすべての情報を提供してしまうのではなく、ブログと同じように、少しずつ、気長に行うのがよいでしょう。
(2)ブログなどのようなストック情報とリンクする
ツイッターであれ、Facebookであれ、ソーシャルメディアの情報が作り出しているタイムラインはすばやく流れ去り、それをあとから見つけ出すことは至難の業です。
そこで、SNSでの発信は、より固定したブログの記事とリンクさせ、詳細はそちらを読んでもらえるように気をつける必要があります。
(3)ゆるやかにフォロワーを増やし、クラスタを発見する
模型のクラスタや、特定のアニメ番組のクラスタが存在するように、あなたのフォロワーは、あなたのクラスタです。あなたが地道に発信している内容にどこか魅力を感じて横目で見ている、潜在的なファンの集合なのです。
『テクニウム』(みすず書房)の著者ケヴィン・ケリーは「1000人の本物のファン」というブログ記事で、あなたがどんな発信をし、どんなプロダクトを生み出したとしても、絶対にそれに目を通して購入してくれる熱量の高いファン1000人ほどいれば、クリエイターとしての活動を維持できると指摘しています。
★1年、3年、5年の知的生活の目標を設計する
最初の1年
最初の1年は挑戦している分野の構造を手探りで知るだけで終わる可能性が高いでしょう。
それでも1日に約2時間、1年で730時間あるならば、外国語の基礎は学べますし、プログラミング言語の基礎に習熟して最初のGitHubプロジェクトを立ち上げるところまではいけます。「誰にでもできるかもしれないが、手を動かさなければ不可能な境地」に足を踏み入れるには十分な時間なのです。
この1年が終わる頃までに、蓄積した情報を発信しはじめるブログを開設するのはよい目標になるかもしれません。知った情報を整理してブログの記事をたとえ10本書くだけでも、それなりの蓄積はできていなければいけません。1年というのは、ちょうどいい準備期間なのです。
2〜3年の目標
3年目の目標としては、浅瀬をぬけて一気に深みに到達するために自分の専門領域、つまりはニッチの開拓が挙げられます。一つのジャンルのサブジャンルを網羅してみたり、一人の作家の全作品を読み切ったりといったアクセルの踏み方をして、愛好家からマニアに進むのもよいでしょう。
3年ほどになると、ブログ記事などの情報発信もある程度数がそろってきます。週に2回の更新でも300本の記事があれば、一つの体系立った本にすることもできます。そこで、これらの記事からベスト30ほどを選び、セルフパブリッシングに挑戦するのにもいいタイミングになります。
4〜5年の目標
このあたりから知的生活の積み上げは、ゆっくりとしたライフワークを追い求める流れと、1〜2年のすばやい流行や自分のなかでのマイブームを追う流れとが自然に重なり合うようになります。「この分野については譲れない」という専門性と、その専門性の周辺を衛星のようにめぐる興味とを区別して追うことができるようになります。
このタイミングは古い情報をもう一度吟味する時期でもあります。私は毎年秋になると、必ず自分の人生を変えた本を再読するという習慣をもっていますが、そうした本からは何年経っても新しい発見と感動を見つけ出すことが可能です。
同じように、時間をかけて深めてゆくテーマと、日々の流行を追うテーマが両輪としてあると、知的生活は長い時間をかけたライフワークと日常の刺激の両方を満たすようになります。
感想
◆「知的生活」にとってブログは最も有益なツール
今回のエントリーでなぜブログに関する部分を中心にメモしたかというと、今、よく「ブログはオワコン」という言葉を耳にするからです。
これはちょっと気をつけてほしいのですが、たとえば有名なブロガーのイケダハヤトさんも「ブログはオワコン」とおっしゃってるんですね。
ただ、これは「SEOで集客してアフィリエイトで設けるツールとしてのブログ」はもう終わっているというかなり限定された意味合いでのこと。
お金儲けのツールとしてはどうかわかりませんが、「知的生活」のための情報を蓄積したり、発信したりするのには、いまのところブログ以上に優れたツールはないと断言できます。
これまで、Twitterなどの後発のSNSが登場する度に「もうブログいらない説」がお決まりのように登場しました。
しかし、依然としてブログの有益性は変わりませんよね。
情報をストックし、タグ付けやリンクも貼れ、検索性もいい。
おまけに動画の埋め込みなどできて、新しいメディアとの連携も随時対応していってくれる。
ちょっとこれ以上のツールはないですよ。
特に情報がフローではなくストックであることの強みは絶大で、古い記事が新しいつながりを作ることも多々あります。
こんな便利なツールを利用しない手はないです。
特になにか夢中になるものがある、ライフワークがある人にとって、ブログで情報をストックして後悔することで得られる見返りは非常に大きなものとなります。
昔だったら、自分の紙のノートに書いて終わり。
運が良ければ紙の本として出版できる可能性もありましたが、それが多くの人に読まれるかどうかはまた別問題。
おそらく、世界中に〇〇アニアとか〇〇愛好家が無数に存在するはずですが、ほとんどの方が無名のまま誰にも知られずに生涯を終えていた事でしょう。
ところが今は誰でも、今この瞬間から発信できる時代。
TwitterやInstagramのアカウントさえ取ればすぐに発信者になれます。
問題はそれを継続する場合に”母艦”になるようなツール。
それはいまのところブログが最適なのですね。
「知的生活」を意識して、10年後にコツコツ積み上げていこうという方、ぜひ本書を参考にブログを始めてみてはいかがでしょう。
もちろん本書はブログ意外にも知的生活のための方法を細やかに解説してくれています。
たぶん日本で問題となるのは”書斎”でしょうね。
環境を整えるのもすごく大切なポイント。
物理的なスペースの問題を解決する方法もいくつか紹介してくれています。
10年後の自分に向けてスターを切りたい方にぜひ。
目次
はじめに あなたの「知的生活」を設計しよう
SECTION01 知的生活とはなにか
SECTION02 人生を変える「知的積み上げ」の習慣
SECTION03 パーソナルスペースとしての「書斎」設計
SECTION04 情報整理と情報発信の戦略
SECTION05 習慣とツールによる知的生活ハック
SECTION06 知的投資と収入のための「知的ファイナンス」
SECTION07 10年後の人生を設計する
おわりに 知的なあこがれを伝えてゆく