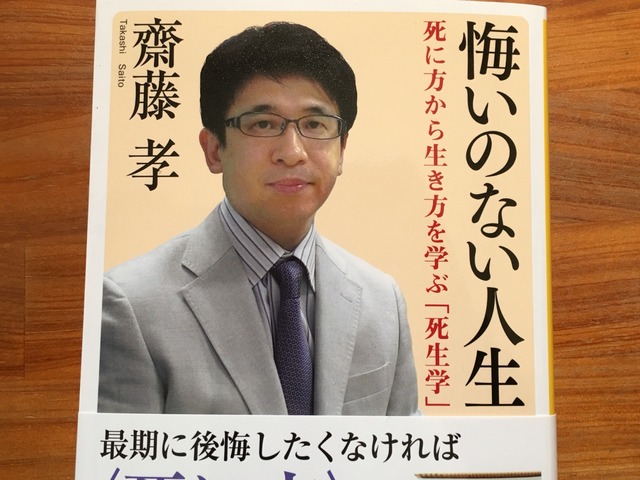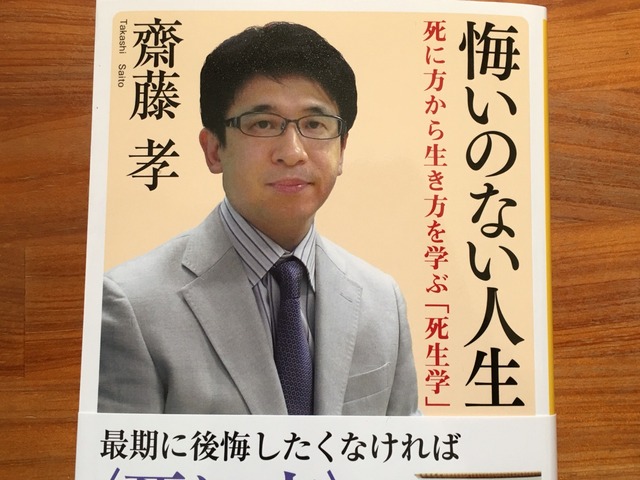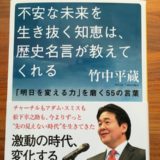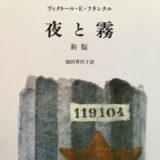おはようございます、一龍です。
誰しも、自分の思い通りの人生をいきたい、せめて悔いのない人生を送りたいと思いますよね。
しかし、実際どう生きればいいのかは難しいテーマです。
今回は齋藤孝先生の「生」と「死」から悔いのない人生を考察したこちらの本、『悔いのない人生 死に方から生き方を学ぶ「死生学」』の中から、『葉隠』を題材に書かれた 第2章 悔いのない最期を迎えるために より、 悔いのない人生を生きるためのポイントを紹介します。
『葉隠』に学ぶ悔いのない人生を生きるためのポイント
★『葉隠』とは
『葉隠』といえば、
「武士道とは死ぬことと見つけたり」
と言う言葉が非常に有名です。
『葉隠』とは、
本書は、安定期を迎えた江戸時代中期に、肥前国佐賀鍋島藩の藩士だった山本常朝の話を田代陣基(つらもと)が筆録したものです。
『葉隠』は全11巻からなり、死に方ばかりを書いているのではなく、主なテーマは奉公する人間の心得です。
戦国時代もはるか昔となり、合戦もなく、武士もめったに死ぬことがなくなった時代に、武士はどう生きるかをテーマにして書かれているのが『葉隠』です。
そう、「死ぬことと見つけたり」といいつつ、「どう生きるか」を説いたのが本作品です。
「死ぬことと見つけたり」とは生の覚悟なのです。
実際、山本常朝自身、60歳という当時としては長生きの一生を全うしています。
★死ぬことを意識することが、生きる力を生む
著者の齋藤先生は三島由紀夫の言を借り、
「武士道とは死ぬことと見つけたり」という有名な言葉が「この本全体を象徴する逆説」である
としています。
その理由として、「武士道とは死ぬことと見つけたり」の後に続く文章に
二つ二つの場にて、早く死方(しぬかた)に片付くばかり也。別に子細なし。胸すわって進む也。(『葉隠』聞書第一)
「二つ二つの場にて」とは、死ぬか生きるかの時を指しています。そういう万が一のときに、「死ぬ方に片付くばかり」だと覚悟していれば、腹が据わって前に進むことができるという意味です。
とあります。
死ぬことを意識するから、生きる力が生まれてくる。
これは僕もかつて死を意識する病気をした体験からよくわかります。
人生には限りがあり、そのゴールは死であること実感できる経験をした瞬間から、周りの景色が変わります。
毎朝目覚めたこと、今日も生きられることを感謝するようになります。
死を意識することで、よりよく生きようとする意識が芽生え、生きる力が生まれるのです。
★「死」の選択肢が自由を生む
さらに続く文章には
毎朝毎夕、改めては死々(しにしに)、常住死身(じょうじゅうしにみ)に成て居る時は、武道に自由を得、一生落度なく家職を仕課(しおお)すべき也。(『葉隠』聞書第一)
毎朝毎夕、「改めては死に、改めては死に」と、日々「自分は死ぬんだ」と死に身の覚悟で生きる。そうすれば自由を得て、仕事もミスせずにちゃんとできるのだ
と書かれています。
どうして死身の覚悟で生きることが自由を得ることにつながるのでしょう。
武士には名誉を守るための切腹という「積極的な死」の選択が可能でした。
死すら選択可能な行為だと考えることで、どんな束縛をも突破でき、自由になれるというのが武士道だったということです。
この生き方について著者の齋藤先生は実在主義の「被投的投企」という概念で説明されています。
私たちはこの世に投げ出されている存在で、どんな環境に生まれ落ちるかを選ぶことはできません。
しかし、生まれた後からは自分の人生を自分自身で主体的に決めることができます。
人生にはいろいろなしがらみがあり、自分の重いとは違う生き方を強いられる時が多々あります。
不条理なことを要求されることもあります。
しかし、死という究極の選択権は常に自分にあるということです。
三島由紀夫は
「切腹という積極的な自殺は、西洋の自殺のように敗北ではなく、名誉を守るための自由意志の極限的なあらわれ」
としています。
ここでけっして誤解してほしくないのは、僕は自殺をすすめているわけでも美化しているわけでもないということです。
あくまで、これは武士道の話であり、現代を生きる我々は「死んで身の潔白を証明する」とか、「死んでお詫びする」などといった行為をするべきではありません。
ただ、心の持ちようとして、武士には死を選択する自由があったということです。
★一瞬一瞬を大切に生きよ
では、現代を生きる我々は、常朝の教えをどう活かし、どのような生き方をすればいいのでしょう。
常朝は次のように言っています。
端的只今の一念により外はこれなく候。一念一念と重ねて一生也。ここに覚え附き候へば、外に忙しき事もなく、求むることもなし。ここの一念を守って暮すまでなり。皆人、ここを取失ひ、別に有る様にばかり存じて探促いたし、ここを見附け候人なきもの也。守り詰めて抜けぬ様になることは、功を積まねばなるまじく候。されども、一度たづり附き候へば、常住になくても、最早別の物にてはなし。この一念に極まり候事を、よくよく合點候へば、事少なくなる事あり。この一念に忠節備り候也と。(『葉隠』聞書第二)
まさに現在の一瞬に徹する意外にない。一瞬、一瞬と積み重ねて一生となるのだ。ここに考えがおよべば、ほかにあれこれとうろたえることもなければ、探しまわることもない。この一瞬を大切にして暮らすまでのことだ。一般の人は、ここのところを間違って、別に人生があるように思い、それを尋ね回って、この点に気づく者がない。この一瞬をいつも大切にして怠ることがないようになるには、年功を積まなければならないものである。しかしながら、一度その境地にたどりつけば、いつもそのように思いつめていなくとも、その境地をはなれることはない。
この一瞬にすべてがあるということを十分に心得たならば、物事は簡単に運ぶものだ。(奈良本辰也『葉隠』知的生き方文庫)
「一念」とは「一瞬」の意味です。
「一瞬一瞬を大切にしなさい」と説いていて、これは禅の死生観である「現在の一瞬を生き切る」に通じます。
現代を生きる我々にとって、日々の生活の中で「死を意識して生きる」のは難しいことです。
しかし、
死というものをことさら挙げなくても、この一瞬をかけがえのないものだという意識を持って生きる。その覚悟があれば、人生に迷い悩むこともなくなるのだ
と常朝は言っているのです。
★この世はしょせんからくり人形の世界
「死を覚悟して生きる」「一瞬一瞬を生きる」といったことを説いた常朝ですが、齋藤先生は最後に『葉隠』から非常に印象的な一節を引用しています。
それは以下の一節
道すがら、何とよくからくった人形ではなきや。糸を附けてもなきに、歩いたり、飛んだり、はねたり、もの迄も言ふは上手の細工也。來年の盆には客になるべき。さても、あだな世界かな。忘れてばかり居るぞと。(『葉隠』聞書第二)
道すがら、常朝が「私たちはなんとよくできたからくり人形ではないか」と語ったという場面です。「糸もつけていないのに歩いたり、飛んだり、跳ねたりして、ものまで言うとは手の込んだ細工だ。来年のお盆には死んでお客になるかもしれぬ」と言い、「さてもむなしい世の中だ。人はそんなことをすっかり忘れているが」と続きます。
「えっ?」って思いますよね。
それまでのテイストとはぜんぜん違う。
齋藤先生も
「死ぬ気で生きろ」と言っている人物が一方で、「この世はしょせん一種のからくり人形の世界だ」と言う。このバランスの取り方がとても面白いと思います。
とおっしゃっているように、ピリピリとした緊張感の中でふっと息を抜いた感じです。
この生に対する意識のコントラストは、両極端なため非常に印象的です。
どこか「人生なんてそんなもんさ」「どんなに頑張ったってしょせんいつかは死ぬのさ」と、醒めて達観した感じがします。
おそらく人間は「死ぬ気で生きる」覚悟を決めても、その覚悟のまま一生をまっとうすることはできないでしょう。
それは大変なストレスになります。
「ON」ばかりではなく、どこかに「OFF」の状態になれる場所や時間をもち、バランスを取らなければ申請というマラソンを走り切ることはできないでしょう。
また、「所詮こんなもんさ」という一種の「諦め」を持っていなければ、どんなに成果を上げた人でも死ぬ間際に後悔する事になるのではないかと思います。
そういえば、豊臣秀吉の辞世の句に「なにわのことは夢のまた夢」の文言がありましたよね。
天下を取った人といえども、死は訪れるし、やり残したことがあるでしょう。
一瞬一瞬を一生懸命生きることはもちろん大切ですが、心の何処かで「所詮自分は舞台で操られるからくり人形」といった達観した人生観をもつことも、悔いのない人生を生きるために必要なのではないでしょうか。
感想
以上、『葉隠』に関する記述の部分から、常朝の死生観、そしてどう生きるかをピックアップしました。
本書冒頭部分に
人生が有限であることを意識することで、よりよく生きようとする意志が生まれてきます。つまり、死を考えることは最大の自己変革につながるのです。
とあります。
人間は自分がいつか必ず死ぬということを知っています。
しかし、頭では理解していても、自分がいつか死ぬということをほとんど意識せず生きています。
僕もそうでした。
しかし、上記したように、病気をして「自分がいつか死ぬ」ということを実感できてから人生観が大きく変わりました。
ですので、「死を考えることは最大の自己変革につながる」という考えはよくわかります。
もっとも、僕の場合はまだ何事もなしえていませんが。
ただ、ダラダラとしたり、いつまでも朝寝したり、お酒に酔って時間を無駄にしたりといったことは無くなりました。
人生の有限性を知り、自分がまだ成したいことを成し得ていないという現状を考えた時、じっとしてはいられなくなったのです。
こういった”貧乏性”的な生き方がいいのか悪いのかは、人生が終わってみなければわかりません。
「自分はもっとのんびり生きたい」という方もいるでしょう。
人それぞれでいいと思います。
ですが、もしあなたが「自分はこうなりたい」「こんなことを達成したい、実現したい」といったものが有るのなら、「死」というものを意識することがエネルギーに変わるかもしれません。
いずれにしても、たとえからくり人形であったとしても、自分の役を演じきって舞台をさりたいと思います。
本書はSBクリエイティブ様から献本していただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに 〈死〉を考えることが最大の自己変革につながる理由
第1章 死の孤独と距離を置く
吉田松陰の『留魂録』 ~処刑前日に書き終えた魂魄の叫び
第2章 悔いのない最期を迎える
『葉隠』 ~現代にも役立つ武士の死生観
第3章 老いと上手に付き合う
貝原益軒の『養生訓』 ~長寿社会における真の養生とは何か
第4章 病とともに生きる
正岡子規の『病床六尺』など ~病を得たからこそわかる価値
第5章 その瞬間まで精神を保つ
V・E・フランクルの『夜と霧』、『きけわだつみのこえ』 ~極限状況の生が教えてくれること
第6章 遺してゆく人々のために
西郷隆盛の『西郷南洲遺訓』ほか ~家訓に学ぶ現代にも通じる遺言の心得
第7章 死者の魂に思いを馳せる
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』から最古の文学『古事記』まで ~物語から読み解く霊的な旅