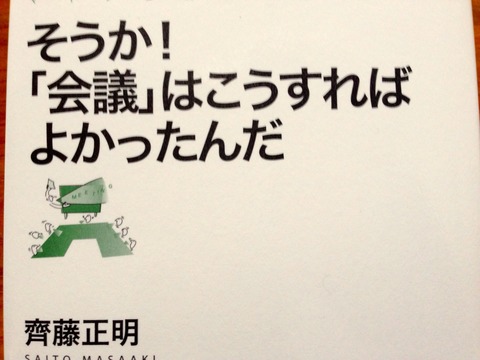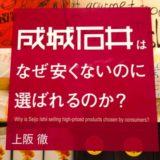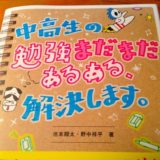おはようございます、会議は瞑想の時間にしている一龍です。
今日は当ブログでもおなじみ、私も大ファンのマグロ船評論家、齊藤正明さんの本をご紹介。
これまでの自虐寝た満載の本かと思いきや、なんと! まじめなテイストのビジネス書に仕上がっていました(←失礼)
はじめに
マグロ船評論家として活躍されている斉藤正明さんの今回のテーマは「会議」。
人材コンサルタントとして、多くの企業研修にも携わる齊藤さんだけに、多くのダメダメ会議も目の当たりにしてこられたのでしょう。
そこから得た会議の改善方法を本書では公開してくれています。
まずはその一端をご覧ください。
会議が活性化するポイント
★「参加者4名、30分、3議題」
私の考える理想の会議は,「参加者4名、30分、3議題」で行う会議です。
人数が多い会議だと、お互いに遠慮し合ったり発言時間が短かったりして、意見が出なかったり無難な結論の会議になりがちです。
とはいえ、人数が少なすぎると、それはそれで意見の幅が少なくて活発な議論になりません。斬新な意見を交えながら、ダラダラした会議にならない参加者の最小人数は4人程度ではないでしょうか。
会議の時間はできれば30分。これぐらいの時間の会議なら、ダレズに緊張感を保った議論が維持できます。また時間が30分だと参加者の都合がつきやすく、必要な会議が迅速に行えます。
それで、会議の議題は三つ。とはいっても、<中略>実質ひとつの議題を三つに分けて議論するというものです。
★「話し合う」ではなく、「聴き合う」
私は「話し合う」ではなく、「聴き合う」を提案します。だからといって、決して「上司の意見を黙って聞いていなさい」という意味ではないですよ。本来の意味での”話し合い”をすればいいんです。
当たり前ですが、お互いの意見を「それは一理ある」と思って聞かないと、良い答えが出ません。
必要なのはチームワークです。お互いにパスを回して、ゴールを目指して、誰かがシュートを決めればいい。その得点は、特定の誰かの手柄ではなく、チーム全員の得点です。
会議も同じ発想で臨んでください。会議中にまわりにいるのは同じチームメイトです。会議で良い結論を出すための味方なんです。
★「目標(ゴール)」を設定する
毎月、毎週、少なくない人数の勤務時間を投入して、定例会議を開いても何も生み出されない。まさに時間の無駄になっています。
その理由は明らかです。
事前に会議の「目標(ゴール)」をしっかり設定していないからです。<中略>会議での目標(ゴール)は、「この会議は何が決まったら、終了できるのか?」です。<中略>
とにかく、何が決まったら会議が終わるのかを定めておく。その目標(ゴール)がないと、会議が白熱した際に、何のために話し合っているのか忘れてしまいがちなんですね。
会議、特に「意思決定」のための会議は、「目標(ゴール)」に対して何か決まったら(あるいは決めないことが決まっても)、それが終了の合図です。決して、決められた時間がきたら終わり、ではありません。会議は早く終わる分には、何の問題もありません。どんどんゴールを決めて、さっさと終わらせましょう。
★「議題」づくりのコツ
会議でゴールを決めるために実際に考えなければいけないことは、より具体的な「議題」です。
議題自体は、会議ごとに違って当然ですが、会議でどんな道筋で話し合っていくのかが、見えやすい議題のほうがいいでしょう。その意味で、私は三つの議題をつくるとスムーズにいくと考えています。その1 問題点を挙げるだけ挙げてみる
その2 1で挙げた問題点で一番ネックになっている点を解決するには?
その3 1、2で話し合ったこと意外の新しい解決方法はないか?を皆で話し合う一つの目標(ゴール)につき、この三つを話し合うと効果的です。
★レジュメは必ず事前に用意する
会議の司会者は、会議で話し合う内容を、事前にレジュメにまとめておきましょう。
もし忙しければ、レジュメの作成自体を別の人にまかせてしまってもいいですが、作成することによって、会議の趣旨や必要な準備、流れが理解できますし、会議の目的、目標は主催者(決定権者)が決めることが多いので、できれば、司会者が行えるのなら、行ったほうがいいでしょう。
レジュメの内容は、基本的にこれまで説明した「目的」「目標(ゴール)」「議題」までを書いておけば十分です。
そして事前に参加者に配布するんです。
★会議には「根回し」が必要?
私が言う「根回し」とは、会議中に演じてもらう。”役割をお願いする”という意味のものです。<中略>
例えば、よく会議で他人の意見の批判ばかりする参加者がいるとします。そのときは、彼と仲がいい人物に「また彼の批判グセが出たら、うまくなだめる役をお願いします」とひと言、言っておくんです。<中略>
あるいは、若い人を攻撃しがちな年長者の参加者がいた場合、別の年長者に「『彼の意見は評価できるよ』などと、若手を守ってあげてください」とお願いしてみてもいいでしょう。
★”落としどころ”より大事なことがある
大事なのは、皆で決めたという納得感を共有することです。
一番避けたいのは、皆が真剣にやらないような、シラケた結論を出してしまうことです。これは会社としては困ります。逆に言えば、皆が「よし、やろう!」と思える結論なら、落としどころありきの会議でも問題ありません。
こういうふうにお話しすると、「やはり正しい決定が大事だ」という方がいらっしゃいます。しかし、「絶対にこれが正解というものがない」のがビジネスです。
それは、あくまでも結果論で、本当にその結論が正しいかどうかより、参加者全員が「決まったことをやろう」という意識になる結論を導くほうが、良い成果を得ることができるのです。
★会議進行のキモは二つだけ
「アイデア出しと、まとめる過程は、必ず分ける」
これこそ、会議の生産性を高めるためのキモといっていい要素です。<中略>
アイデア出しの段階では、一切の制限を取っ払うんです。
そこで初めて皆に、参加者意識を芽生えさせることができます。グッと発言しやすくなるわけです。そして一つでも発言できると、その会議に参加した意識を感じて、決定事項を守ろうとする気持ちが芽生えるのです。
まずアイデアを出すだけ出させる。そして出尽くしたところで、一つに絞っていく。問題は、どの段階でアイデア出しを終わらせるかですが、時間て区切る必要はありません。場を見ていれば、明らかに出尽くしたなという空気になるはずです。
そこから「まとめる作業」よに移りましょう。
感想
◆めざすのは納得感の共有だったのか!
冒頭でも書きましたが、私にとって会議は瞑想の時間です。
というのも、私の職場の会議は完全な上意下達の場で、”決定事項の報告”がメイン。
なのにときどきごねたり、反対したり、持論を長々と展開したりする人がいて時間だけは長くなるというもっとも瞑想に向いている時間です(笑)。
だから「会議」と聞くと、「どうせ発言しても無駄」と、ネガティブなイメージが先行してしまうのです。
そのため本書で、会議の目指すところが
大事なのは、皆で決めたという納得感を共有すること
というのは目から鱗でした。
◆司会者の力量
「納得感を共有」できる会議にするためには、もちろん参加者全員の強力が必要です。
しかし、
会議とはみんなで良い結論を出すのに向かって話していく創造的な場
という雰囲気を醸し出し、ゴールへ導くのに大きな役割を担うのはやはり司会者でしょう。
本書では、会議の準備段階から会議中の細かなテクニック、そして結論を出す方法まで丁寧に解説してくれていますが、そのほとんどが司会者の役割に関するものです。
確かに司会者は重要。
私の職場の”決定事項の報告”がメインの会議ですら、司会者(毎回順番で持ち回りだから下手な人もいる)がグダグダだと収拾がつかなくなって、どんどん時間だけが過ぎていく状態に突入しますから。
そこで私思うのですが、司会専門職を作ってみてはどうだろうと。
○○部長とか、××係長とかと同じで、司会部長なんてだめですかね。
それが無理なら、せめて、人望が厚くて、会社の仕事に広く精通していて、新人から社長まで「この人なら」と一目置かれている人を数名ピックして、会議の仕切り方を徹底して訓練するというのはどうですか?
司会というかファシリテーターを養成しておくのです。
無駄な時間ばかりで生産性のない会議がずっと続くぐらいなら、思い切ってこういう取り組みも長い目で見れば絶対お得だと思うのですけとね。
◆「会議は真剣にやらない」
さて、本書では齊藤さんお得意の”マグロ船ネタ”があまり登場しません。
が、やはり齊藤さんの主張の基礎部分はマグロ船での体験で形成されているのでしょう、重要なキモの部分でチラッチラッとマグロ船ネタが登場します。
その中でも本書のテーマで重要な考え方が、「会議は真剣にやらない」というもの。
漁師たちのたわいない会話に、齊藤さんが生真面目に答え、しかもつまらない顔をしていたのを見て、マグロ船の船長が諭すシーンで
「別にマトモな意見なんぞ求めちょらん。みんなで話しよるときはの、大事なんは”正しいことを教えること”より、”応援してやろう”と思う気持ちぞ」
「意見なんてくだらなくてエエんど。くだらねぇ意見には、『くだらねぇ意見でも言っていいんだ』ってゆーのが、まだ自信のねぇ若ぇ子にも伝わるけぇのぉ。船で困るんは、気づいたことを報告せんようになることじゃけぇ」
このエピソードから齊藤さんは
会議は真剣にやらない。むしろみんなの意見を応援するぐらいの気持ちで話さないと、会議は活性化しない
という教訓に到達します。
「真剣にやらない」というと、ちょっと抵抗がありますが、意見の出ない風通しの悪い組織は硬直していずれ衰退していくもの。
そう考えると、いままでつまらないだけだと思っていた会議の重要性に気づきますよね。
大げさではなく、その組織を生かすも殺すも会議次第。
そして会議はみんなで作り上げていくものですが、多くの部分を司会者の力量が負うところだという現実を考えたとき、本書で司会者はテクニックを身につける必要があるのではと思います。
会議の活性化が組織を強くする。
あなたの会社の会議が「無駄だ!」と感じているのなら必読です。
本書は著者の齊藤正明様から献本していただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに
序章 ほとんどの人が間違えている!会議に対する誤解
第1章 会議は事前の準備がすべて
第2章 会議の序盤でやること、心がけること
第3章 意見が活発に出るよう上手に仕切る技術
第4章 みんなが納得できる結論を出すために
第5章 会議の「困った!」を解決する
おわりに
関連書籍
齊藤正明さんの既刊本をいくつかご紹介