当ブログではおなじみ、水野俊哉さんの久々の新刊です。
そして間違いなくこの本は水野さんの代表作となる本です。
はたして水野さんの伝えたいことは何なのか?ジェットコースターのような人生経験から得たものは何か?
【目次】
はじめに
Chapter1 欲望とカネの世界
Chapter2 こうしてお金の流れは止まる
Chapter3 脱出不能の借金の穴
Chapter4 地獄で知った「お金のからくり」
Chapter5 幸福の商社、不幸のデパート
【ポイント&レバレッジメモ】
本書は私小説、あるいは伝記的な本ですので、ポイントのまとめというより気になった部分をいくつか抜き書きしました。
美女たちは「おごってくれる金まわりのいい男」と知り合いになりたくて集まってきて、ハイステータスのVIPはきれいどころによる奉仕が無料で受けられる。
「結婚とは顔と金の交換である」と言った社会学者がいたが、このイベント会場でも顔(あるいは若さ)と金(あるいは権力)が等価交換されるマーケットが生まれていた。<中略>
VIPフロアは、そんな卑しい原理をまざまざと見せつける仕組みになっていた。
しかし、いちばんの悦楽は快適な場所から、そうでない場所にいる人たちを見下ろす権利であろう。
まったく、バカと金持ちと煙はなぜ高いとことに上りたがるのか?
だが、当時の僕も高みに登っていい気になっていたのは間違いない。だから堕落したのだろう。
「金で買えないものはない」と書いた本が物議を醸したころだった。
確かにお金には強力な磁力がある。森の中の街灯に色とりどりの蛾や昆虫が集まってくるように、人はお金や権力のあるところに自然と引き寄せられてしまう。
単純に言うと、お金には人の心を動かすパワーがある。
その性質を理解して、自分の感情をコントロールしなければいけない。
金に目がくらんで理性を失った人間の帰結は、フォースの暗黒面に落ちたジェダイの騎士のようなものだ。
お金がもたらす富や権力に欲望を刺激されて感情のコントロールを失うと、際限のないマネーゲームに人生を支配されてしまう。
死ぬほど頑張れば、人生で一度くらい金にまみれた生活を送ることはできるかもしれない。
だが金を目的にして働いて、多くの人に尊敬される永続的な成功がもたらされることはない。そして、使いきれないくらいの金をつかみ、どんなに派手な暮らしをしても、それだけで人は幸福感を味わうことはできない。
少なくとも、誰かと比べて買っている負けているという発想をしている限り、いつまでも心の安らぎを感じることはできないのだ。
金で買える快楽はシャンパンの泡のようなもので、すぐに消えてしまう。
人の心や健康や愛情や人間関係は金で買えないし、金とは関係ないのだ。
つまるところ借金の苦しみは重度の薬物中毒患者のそれとさほど変わらないと思う。
人間の脳は、<中略>爬虫類の脳の上に哺乳類の脳が乗り、その上にさらに高等な哺乳類の脳が乗るという、まるで「3段重ねのアイスクリーム」のような構造になっているという。
真ん中の大脳辺縁系にはアーモンドのような形をした扁桃体があり、生存のために危険を察知さすると、逃走か逃避かを素早く処理している。
つまり、借金が返せなくなると、常に「この状況から抜け出したい」という危険信号が感情や神経を支配してしまうため、理性的な判断力が失われてしまうのだ。<中略>
逆に言えば、それだけの苦しみから逃れるためであれば、人は時に犯罪的な行為に手を染めてしまったり、もはや永久にこの苦しみから抜け出せないと悟れば、いともあっさりと自死を選んでしまってもおかしくない。
このころの経験から学んだことは、お金は「足りない」より「ない」ほうがましだということだ。
人生とは死ぬまでの時間をどう生きるかということである。そのためには、この貴重な一瞬一瞬をどう生きるか考えるための時間が大事なことはいうまでもない。
当時の僕は日々の業務に忙殺されて、ビジネスのことしか考えられなくなっていた。
心の自由は、金銭的な価値でははかれない。そんな簡単なことに気づくために、僕はこれまでいろいろなものを失ってしまった。
僕は世界の中心にいて、ものすごく大事な役割を担っているような気になっていただけだった。
もしも僕が倒れたら、銀行やスポンサーや取引先や部下や仕事の関係者やユーザーやその他含めて10万人、100万人に波及効果的な影響が及んだりする重要人物のような気になっていたのだが、それはまったくもって杞憂であり、そもそもそのような世界観というか、物事の捉え方に本質的な問題があったのだ。
僕が大事だと思っていたビジネスの世界。
それは虚構の世界であり、僕の現実は家族や友人といった小さな世界にこそあったのかもしれない。
地位、名誉、お金に美女たちもいなくなり、人間関係も社会的な信用も、すべてを失ったのに、なぜこうして歩いていることが幸せなのか。それが不思議だった。
成功とか失敗とか、お金持ちとか、収入が高いとか低いとか、大企業に勤めているとか零細だとか、正社員かフリーターかとか、そんなものは心を縛る鎖でしかなかった。
そんな価値観から解放されることの重要さが、すべてをなくした今、心の底から理解できた。
人生には分岐点がいくつも存在する。そしてその多くは右へ行くか左へ行くかの分かれ道ではなく、実は現状に留まるか、未来へ踏み出すかの選択なのである。
人間は変化を恐れる生き物である。
誰しも暗闇に一歩を踏み出すのを恐れるものだ。
だが、恐怖心とは頭の中で生み出された幻想にすぎない。それは借金地獄の中で身をもって知った教訓のひとつだった。
ちょうど、僕が隣の家の庭の木を恐れたのと同じように、勇気を持って踏み出した先に待っているのは、あなたが望む未来なのだ。
労働の対価として受け取る報酬は環境次第であり、給与の額は必ずしも人の能力や評価をそのまま反映しているわけではない。
だから給与のが気宇が自分の能力だと考えるよりは、自分が本当にやりたい仕事についていて、お客さんや世の中に貢献できているかどうかで考えるべきである。
そうした働き方になれば、もはや、経営者だろうが従業員だろうがフリーランスだろうが関係ない。「それをやること」が喜びになるような仕事で働ければ人は幸せになれる。
いま、執筆の仕事をしていて僕はつくづくそう思う。
【感想など】
以前の記事
「署を捨てよ、街へ出よ」【旅日記】東京紀行4日目(8月29日)
で、
ここだけの話ですが、水野さんの次回作は必読です!
作風もガラッと変わりますよ。そして、水野さんの代表作になる傑作です。
たくさん本を読んでいると、時々、
「この人はこの本を書くために生まれてきたんだな。これを書くことがこの人の人生のお役目なんだな」
と思える本に出会えます。水野さんの次回作がまさにこれ。乞うご期待。
と予告した本が本書です。
まさに著者である水野さんご自身も”お役目”の部分は感じているようで、本書内に
圧倒的な多幸感の中で、僕は思った。
僕が失い続けて最後に見たものを書くために、僕は生かされているのではないかと。
いや、本当の僕は2006年の冬に死んでしまったのかもしれない。
それでも同じことだ。
こうして本を書き続けていくことで、身近な人に貢献することが、僕の生きる意味だと僕は思っている。
と書かれています。
読書の価値にはいろいろなものがあると思いますが、そのひとつには「別の人生を疑似体験することによる学び」があると思います。
特にビジネス書の場合は、文芸のフィクションと違って著者の経験から書かれたもの。
有名経営者の成功体験は、それはもちろん読んで価値あるものと思います。
しかし人間は失敗談に関しては、「あのときは大変だったよ」と笑い話にできるレベルの苦労話なら語りたがるものですが、ある水準を超えたものは隠したくなるものでしょう。
しかし失敗からも実は大きな学びが得られるもの。
そういう意味で、本書は非常に貴重な本だと思います。
多分水野さんご自身は、「別に隠してたわけじゃないですよ」とおっしゃることと思いますが、普通なら心の奥底にきっちり封印して墓場まで持っていきたくなるであろう経験を、ここまでありのままに表現されたことに敬意を表したいです。
そこに作家としての強い使命感を感じます。
ぜひ、多くの方に水野さんの人生経験をシェアしていただきたいと思います。
さて本書は、簡単に言うと 成功 → 失敗 → 再起 の三部構成になっています。
バブルを知らない若い方には、前半の2000年代最初のITバブルからベンチャービジネスが跋扈した頃の本書前半部分を読んでどう感じたでしょうか。
水野さんをはじめ、お金に多くの人々が踊らされ、”勝ち組”とか”ヒルズ族”なんて言葉がもてはやされた時代。
この部分を読んで、「俺もベンチャー立上げたい」「起業して勝負したい」と思う方もいるのではないかと思います。
ワタクシはそういったエネルギッシュな若者がどんどん出てきてくれることが、日本の未来のためには絶対必要だと思うので、恐れることなくガンガン挑戦していただきたいと思います。
ただ、心に深く刻んでおいてほしいことがあります。
それは本書が伝えたい部分。
人生の幸せとは何か?
それをしっかり見つめつつ、自分の夢に挑戦してほしいのです。
お金で買える幸せというものも世の中にはあるのでしょう。
けれど、それは根源的な幸せなのか?そして、お金を目的にした人生はそれほど価値ある人生なのか。
水野さんのようにすべてを失い、3億円の借金地獄に堕ちてから本当の幸せに気づく。
そんなことがないように、本書を読んでしっかり考えてほしいのです。
ワタクシ、今日はちょっと上から目線で書いています。
もちろんワタクシなど、起業したこともないし、「月の可処分所得が200万円以上」なんて一度たりとも経験したことありません。
じゃなんで説教臭いことを言っているかと申しますと、ワタクシも本当の幸せとは何かを身をもって体験する出来事があったからです。
水野さんが借金地獄の中で苦しんでいた2006年は、ワタクシにとっても人生のターニングポイントでした。
脳腫瘍が見つかり、医者に「まず左半身不随になってそれから意識不明。最終的に死にいたります。」と宣告された年でした。
スティーブ・ジョブズの言い方を借りれば、「私の人生で一番死に近づいた」時期がちょうど水野さんの借金地獄の時期なんです。
幸運にもスーパードクターに出会い、12時間にわたる手術を秋と冬の二回行ってもらって、寿命を延ばしてもらうことができました。
そのときわかったのが、水野さんが言うように「死ぬこと以上の不幸はない」ということ。
そして、「生きていることの幸せ」でした。
ベッドから起きられるようになるだけで幸せ。
歩けるようになることが幸せ。
ご飯が食べられることが幸せ。
朝目が覚めること、今日も生きられることが幸せ。
幸せというのは空気みたいなものかもしれません。
普段は見えないしあって当たり前、でもどん底の状況に追い込まれたときに、ようやく気がつくんですね。
何でもないことの幸せを。
どうか、特に前途ある若者諸君は本書を読んで深く考えてください。
水野さんのように借金地獄に堕ちたり、ワタクシのように死に近づいたりすることなく、本当に大切なことは何か、人間にとって幸せとは何かを教えてくれる良書がここにあるのですから。
本書は著者、水野俊哉様から献本していただきました。
ありがとうございました。
【関連書籍】
水野さんが借金地獄から再起し、作家としてスタートを切ったデビュー作と2冊目の本がこちら。
「成功実験のモルモット」になって得たエッセンスがぎっしり詰まっています。
【管理人の独り言】
水野さんとは懇意にしていただいておりますが、本書を読んで不思議な縁を感じました。
2006年冬、水野さんが東京をさまよい歩いていたとき、ワタクシは2度目の手術を受けて病院のベッドの上でした。
そして水野さんが借金地獄から再起し、作家へと転身しようとする頃、ワタクシはブログを始め、コンテンツを書評に固めはじめている頃でした。
「自分が書くもので世の中によい影響を与えたい」と考える水野さんと、「寿命を延ばしてもらったんだから残りの人生は少しは世の中の役に立とう」と考えたワタクシが接点を持ったのは、水野さんの2冊目の本の書評でした。
以後、何度かお会いする機会もあり、ずっと応援することになるのですが、本当に縁とは不思議ですね。
もし水野さんの事業がうまくいっていたら、そしてワタクシの手術が失敗していたら会うことはなかったんですから。
これからもご縁を大切にしていきたいと思います。
なぜならこれはお金で買えないご縁ですから。
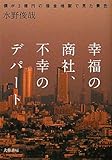


初めてコメントさせていただきます。
とてもとても、勉強になりました。一龍さんの体験からくるお言葉、重く受け止めました。
>人生の幸せとは何か?
そしてお金とは何なのか?
忘れてしまいがちですが、定期的に時間を取って見つめたほうがいいテーマですね。さっそく読んでみようと思います!