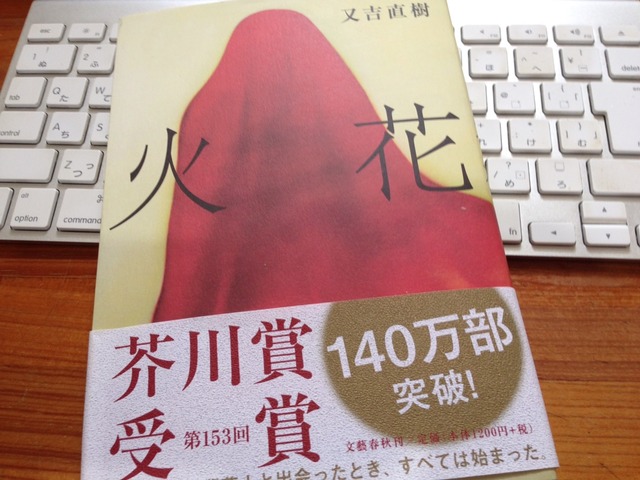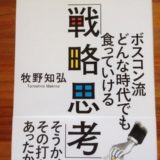又吉直樹さんの芥川賞受賞作品『火花』を読みました。
200万部突破したとか、芥川賞のレベルとしてはどうかとか、何かと物議をかもしている本ですが、印象に残った部分とか感想などを読書メモとして書いておきます。
こういう話題の本を読むというのはちょっと癪に障る感じはあるのですが、本好きとしてはもちろん気になる。
でも買ってまで読むのはなぁ、ブームが過ぎた頃に図書館で借りようかなんてあれこれ思案していたら、実家で母が購入していたのを見つけてちゃっかり借りてしまいました(ナイスおかん)。
挑戦した者にしか得られないものがある
本書は漫才師をめざす主人公、徳永が天才肌の先輩漫才師神谷と出会ったことから始まる物語です。
著者ご本人が漫才師ですので、身近な題材をネタにしており、リアリティがあります。
特に、主人公と神谷との漫才談義の部分は、本物の芸人さんはこういう論議をしているのだろうと伺わせる内容で興味深いです。
特に神谷の漫才論は読んでいてドキッとさせられました。
プロの漫才師である又吉直樹さんに対して、こんなことをいうとおこがましいですが、私もブロガーで書評もどきを書いている”表現者”の端くれとして、以下の神谷のセリフはグサっと刺さりました。
「平凡かどうかだけで判断すると、非凡アピール大会になり下がってしまわへんか?ほんで、反対に新しいものを端から否定すると、技術アピール大会に成り下がってしまわへんか?ほんで両方をうまく混ぜてるものだけをよしとするとバランス大会になり下がってしまわへんか?」
「一つだけの基準を持って何かを測ろうとすると目が眩んでしまうねん。たとえば、共感至上主義の奴達って気持ち悪いやん?共感って確かに心地いいねんけど、共感の部分が最も目立つもので、飛び抜けて面白いものって皆無やもんな。阿呆でもわかるから、依存しやすい強い感覚ではあるんやけど、創作に携わる人間はどこかで卒業せなあかんやろ。他のもの一切見えへんようになるからな。これは自分に対する戒めやねんけどな」
「論理的に表するのは難しいな。新しい方法論が出現すると、それを実戦する人間が複数出てくる。発展させたり改良する人もおるやろう。その一方でそれを流行りと断定したがる奴が出てくる。そういう奴は大概が老けている。だから、妙に説得力がある。そしたら、その方法を使うことが邪道と見なされる。そしたら、今度は表現上それが必要な場合であっても、その方法を使わない選択をするようになる。もしかしたら、その方法を避ける事で新しい表現が生まれる可能性はあるかもしらんけど、新しい発想というのは刺激的な快感をもたらしてくれるけど、所詮は途上やねん。せやから面白いねんけど、成熟させずに捨てるなんて、ごっつもったいないで。・・・」
熾烈な競争の世界にいる芸人さんたちは、日々新しい表現、他とは違う表現を追求していることでしょう。
しかし、仕事の性質上当然批評にさらされ、しかも上下関係のはっきりした世界だけに上からの批評は絶対的力を持つ。
そんなやりにくいところでの切磋琢磨は想像を絶する物があると思います。
それに比べれば好き勝手に書いているブロガーの受けるプレッシャーなどは大したことはありません。
大切なのは、自分の信じる基準、価値観、表現を続けて熟成させること。
結局、誰かの批評で自分を変えたり、他の人の真似をしても絶対に大成しないのだとういうことを、かなり豪速球の直球でズドーンとやられました。
そしてもうひとつ。
(ここからちょっとネタバレあり)
この物語では結局徳永は漫才師を続けることを断念します。
10年もの歳月をかけて挑んだ漫才師の道を終えるにあたって、主人公はこんなふうにいいます。
必要がないことを長い時間をかけてやり続けることは怖いだろう?一度しかない人生において、結果がまったく出ないかもしれないことに挑戦するのは怖いだろう。無駄なことを排除するということは、危険を回避するということだ。臆病でも、勘違いでも、救いようのない馬鹿でもいい、リスクだらけの舞台に立ち、常識を覆すことに全力で挑める者だけが漫才師になれるのだ。それがわかっただけでもよかった。この長い月日をかけた無謀な挑戦によって、僕は自分の人生を得たのだと思う。
「やめてしまえばやらなかったのと同じ」とか、「世の中結果が全て」とかいう人がいます。
たしかにビジネスの世界ではそういう厳しい一面が真理としてあります。
しかし、結果はどうあれ挑戦した者にしか得られないもの、見ることができない景色があります。
それを知ることができる人生と、挑戦しない人生。
どちらを選ぶかはその人の自由な選択です。
挑戦しない人生だって、それはそれで充実した人生になるかもしれません。
挑戦しないことが悪いことだとは言い切れません。
ただ、どちらを選ぶにしても時間は過ぎ、人生はいずれ終わります。
人生の有限性だけは、人生の大きな選択を迫られたときにつねに記憶にとどめておきたい。
そんなふうに感じました。
『火花』の素直な感想
さて最後に僕は文芸書の書評は書けないので、かわりに最後に素直な感想を書いておきます。
まず、芥川賞としてのレベル云々の議論がありますが、僕は芥川賞前作品を読んで比較したことがないのでなんともいえません。
ただ、文芸書として十分にレベルの高い作品であることは間違いないし、お金を払って勝って決して損はしないと思います。
また、著者が芸人であることに起因した厳しい批評がありますが、まったくナンセンスだと言っておきます。
著者の職業なんて関係有りません。
文芸に関する賞の受賞者にはアルバイトで生計を立てている人もいるじゃないですか。
それに比べれば、芸能界で生き残っているその道のプロフェッショナルなのですから、むしろ忙しい芸人がここまで書けたことに対して敬意を払ってもいいんじゃないかと思います。
ところで、この作品の面白かったのは文体の巧みさです。
全体にわりと固めというか、ちょっとクラッシックな文学的表現がなされています。
著者自身意識的に使っているのか、見たことも聞いたこともないような単語が時々登場して、クラッシクな文学的雰囲気を醸し出しています。
ところが、主人公と神谷一芸人同士の会話は関西弁の軽妙な掛け合いで、しかもボケ合戦で全体の固い文体とのコントラストが非常に面白い。
こういう構成って新しいし、ありだなと感じましたし、又吉さんのオリジナリティが出ていると思います。
他の人には書けないという文体が完成している点、かなりハイレベルです。
ただし、日常的に会話の中にボケを意識して話している関西の人にはいいですが、それ以外の地域の方が読むと、最初面食らうと思います。
また、クライマックス(引退舞台)の盛り上がりも素晴らしく、ちょっとウルウルきます。
それでいて、物語のすべてが終わったと思わせてからの未来を感じさせるラストシーンも上手い。
(ぶっちゃけ、次回作に続くことができる終わり方です。)
ただ、あくまで純文学なので、キレッキレのぶっ飛んだ小説を切望している方には物足りない作品であることを言っておきます。
ということで、結論。
読無に値する本!
以上。
『火花』を購入するならkindle本がお得です。
又吉直樹さんの既刊本