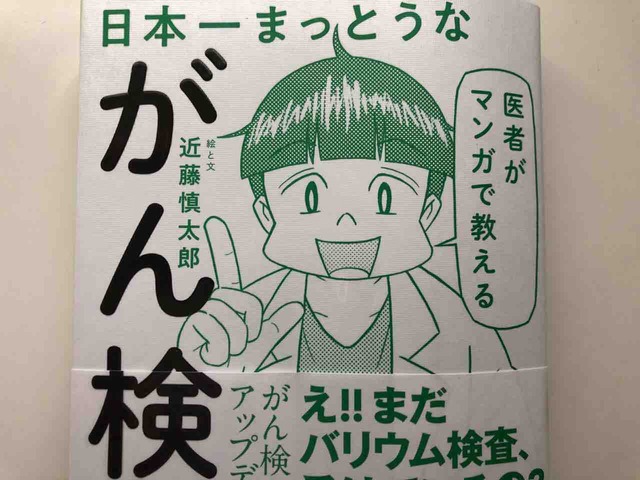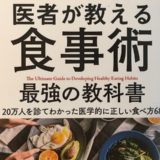こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。
今日ご紹介するのは、近藤慎太郎先生による『医者がマンガで教える 日本一まっとうながん検診の受け方、使い方』です。
著者は消化器を専門とするドクターで、専門的な立場からがん自体とがんの検診の有効性について、なんとご自身で描かれた漫画を交えてわかりやすく解説してくれています。
今回の読書メモは本書で取り上げられているがん(目次参照)の中から、現在行われている検診に何をプラスすると更に効果があるのかという点をピックアップしました。
では早速読書メモをシェア!
『医者がマンガで教える 日本一まっとうながん検診の受け方、使い方』の読書メモ
★肺がん
・レントゲンによる検査によって、肺がんの死亡率は30〜60%下がる
・タバコの影響が強い肺門部がんは、痰の検査を併用することが有効である
・CT検査は、レントゲンによる検査よりも肺がんの死亡率を20%下げられる。ただし過剰診断、被ばくのリスクに注意が必要で、自治体の検診では受けられない
肺がんで助かる人と亡くなる人の運命を分けるものは何か。
先程の疑問に回答するなら、「レントゲンによる検査だけでは時に不十分。自分のリスクに応じて、痰の検査やCT検査を併用することが大切」とういことになります。
あえて弱点を言えば、レントゲンやCT検査の結果は、1枚1枚医師が読影するので、その読解能力によって差が出るかもしれません。
★胃がん
もしかすると、皆さんの中に「ピロリ菌を除菌すれば胃がんにならなくなる」という説明を受けた人がいるかもしれません。
けれど、それは全くの誤解です。き
胃がんの発生リスクを「減らせるかもしれない」というだけで、「ゼロになる」わけではありません。
胃カメラとバリウム検査、両方とも一長一短があり、胃がん検診としてどちらが優れているか(つまり、どちらがより早期の胃がんを見つけるか)は一概に言えません。
ただし一つ、決定的に違うところがあります。
それは、胃カメラの場合は、食道も詳細に観察できるということです。
その結果、早期の食道がんの85%が胃カメラで見つかっており、バリウム検査で見つかっているのは11.2%にすぎません。
★大腸がん
現在健康診断や人間ドックで、大腸がん検診としてまず行われるのは「便潜血検査」です。これは便の一部を容器に入れて提出し、便の中に血液が混ざっていないかどうかを調べる検査です。
では、実際の診断能力のどのくらいの精度なのでしょうか。
報告によってばらつきがありますが、大腸がんを1回の便潜血検査で指摘できる可能性は30〜56%、2〜3回繰り返してやっと84%と言われています。
やらないよりもやった方がいいのは間違いありません。ただし結果を絶対視して安心していると、足元すくわれる可能性が出てきます。ポリープを早期に発見するには、便潜血以外の検査を受ける必要があります。
★膵がん
「進行が早くて早期発見・治療が難しい悪性度の高いがん」
膵がんはたとえステージⅠ期(早期)て見つかっても、5年生存率が50%に達しない
膵がんのように現状では二次予防が非常に難しいがんは、相対的に一次予防のウエイトが大きく、発がんリスクをできるだけ減らすことが重要になるのです。
では、膵がんのリスク因子には何があるのでしょうか。それは次のようなものです。
・がんの家族歴
・慢性膵炎
・肥満
・糖尿病
・タバコ
・アルコール
★乳がん
通常、がんのリスクは加齢とともに上昇します。ところが乳がんの場合、40歳代後半で一旦ピークを迎え、その後60歳代後半から減少し始めるのです。
女性ホルモンが乳がんの発症を促進する方向に働くので、加齢によって閉経するとむしろリスクが減少していくのです。
そしてマンモグラフィーが1番の問題は、病変の見逃しがあり得るということです。
乳腺の濃度が高いと、マンモグラフィー乳房全体が真っ白に写ってしまいます。病変も白く写ることが多いため、真っ白な背景の中に隠れてしまって見逃す可能性が高まるのです。特にアジア人や若い人に乳腺濃度が高いことが知られています。
現状で最も有効なのは、「乳腺エコー検査」を併用することです。お腹や心臓のエコー検査と同様に、乳房に超音波を当てて、がんの有無をチェックすることができます。
先ほど説明したように、乳腺濃度には個人差があり、4グループに分けることができます。
しかし国の乳がん検診の指針では、マンモグラフィーの結果を「異常なし」か「要精密検査」のどちらかで通知するよう定めています。つまり、受けた本人の乳腺濃度がどのグループに属していたかは、原則的に通知されません。たとえ「高濃度で見えづらかった」としても、明らかな問題が指摘できなければ「異常なし」に分類されるのです。
実はこれが、乳がん検診の一番の盲点です。
感想
◆秀逸な癌と癌検診の入門解説書
昨日紹介したこちらの本
でも書きましたが、健康やダイエットに関するものほどトンデモ情報が多いものはない印象を受けます。
しかも厄介なのは、ちゃんと免許を持っているお医者様でも180度違う意見を行ったりする人がいること。
(たとえば、「癌は治療するな!」と、主張しているお医者様もいらっしゃいますよね)
更に悪いことに、僕らは僕らで専門的な知識もないのに、「あの検査は意味がないらしい」とか、「関係機関の利権のために行っている」とか勝手なことをいうわけじゃないですか。
で、僕たち素人は一体何を信じていいかわからなくなる。
結局この件に関しても、多くの社会問題と共通していて、医療に関してたくさん本を読むなりして「見る目」を養うしかないように思います。
そんな伏魔殿のような健康関の世界の中で、本書は非常に公平でエビデンスに基づいており、正直に現在行われている健診方法の欠点も指摘されているなど、非常に好感が持てる、信頼できる本だと判断しました。
著者の人柄でしょう、「伝えたい!」という熱意が感じられるし、癌と癌検診の秀逸なわかりやすい入門解説書だと思います。
◆癌検診は「合わせ技一本!」
さて、本書でよくわかったのは、癌の種類にもよりますが、一つの検診方法で安心しないこと。
僕も今は真面目な勤め人なので、毎年職場で健康診断やら癌検診を受けています。
胸部レントゲン、胃のバリウム検査、便潜血検査はマストです。
ですが、すっかり「異常なし」の通知で安心していました。
それぞれの部位によって1種類の検診では100%でないということを知れたのは大きな収穫でした。
予算や時間の制約はあるでしょうが、できれば、より精度を上げるための検査を合わせて受診することを考える上で本書を参考にしてほしいと思います。
◆僕らができることは検診を受けること、そして生活習慣を見直すこと
また、本書を読んでいて感じたことは、結局僕らにできるのは生活習慣を見直して、いわゆる「一次予防」に努めることしかないということでした。
本書で何度も登場する癌のリスク因子
・タバコ
・肥満
・アルコール
この3つに関しては完全に自己責任(←この言葉嫌いだけどあえて使います)じゃないですか。
特にタバコ。
肺がん以外にも15種類の癌のリスク因子となっているとのこと。
しかも本人だけでなく、周囲の人にも影響を与える”毒物”です。
「喫煙者の権利」「自己責任」「税金を沢山払っている」「そもそも国が発売している」などなど喫煙者は主張しますが、思考停止しているというか、なんか違うんじゃないかと思います。
「喫煙はゆるやかな自殺であり、殺人」ですよ。
僕らは癌検診に頼るだけでなく、生活習慣を見直してがん予防をすることが本来のあり方なんじゃないかと考えます。
幸い本書では、癌検診に関する解説だけでなく、癌のリスク因子に対する知識も得られます。
禁煙方法やアルコールの害についても触れられていますので、ぜひお読みください。
本書は日経BP社様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
あなたが最初にチェックするのは? 「がん検診」早見表
chapter1 肺がん がんの中でも死亡数は第1位! 喫煙者は要注意
chapter2 胃がん 罹患数は減少傾向。だがピロリ菌の除菌は”万能”ではない
chapter3 前立腺がん 男性なら誰もが気になるがん、前立腺肥大やEDとの関係は?
chapter4 肝臓がん お酒好きは要注意。肝臓だけではない、アルコールの破壊力
chapter5 食道がん 急増中の逆流性食道炎と食道がんの悩ましい関係性
chapter6 大腸がん 死亡数はがんの中で2位! 大腸カメラは辛い? 辛くない?
chapter7 小腸がん 消化管の「暗黒大陸」、カプセル内視鏡が検査で活躍
chapter8 膵がん 進行が速く、悪性度も高い! とにかく「避ける」しかない
chapter9 乳がん 若い女性は要注意、検査で見逃さないために
chapter10 子宮頸がん 「HPVワクチン」問題、結局受けるべきなのか
chapter11 PET検査、血液がん検診:最先端のがん検査技術、果たしてどう使えばいい?
chapter12 がん検診懐疑派への反論 制度は満点ではないけれど、受ける価値はある
関連書籍
同著者の関連本。