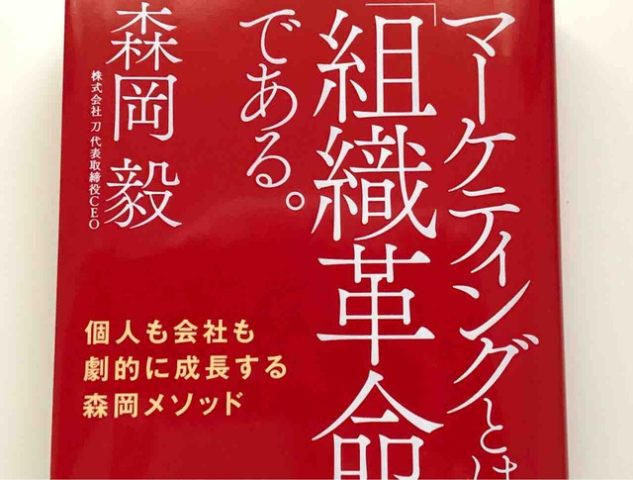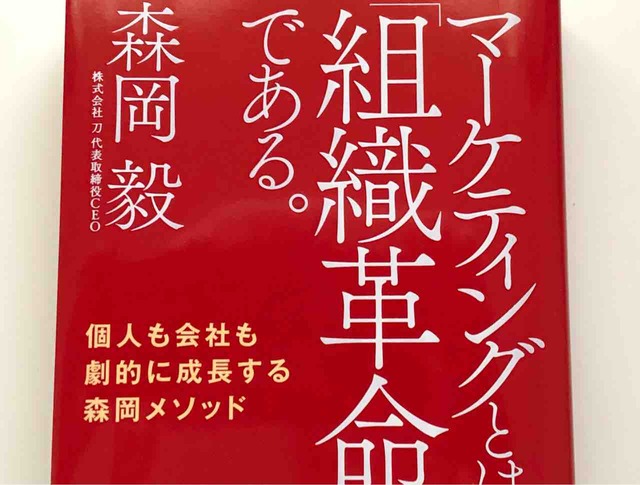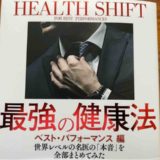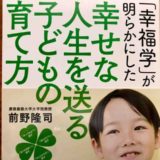こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。
今日ご紹介するのは森岡毅(著)
マーケティングとは「組織革命」である。 個人も会社も劇的に成長する森岡メソッド
では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!
『マーケティングとは「組織革命」である。』より社内マーケティングのための読書メモ
★下のものが組織を変える手法=マーケティングの手法
自分か売りたい「提案」を上に買わせるのは、社内という市場を開拓するマーケティングです。自分が起点になって組織を変える力、それはまさに社内マーケティング。組織改革に限らず、あらゆるご自身の提案を社内で通すときに有用な考え方です。
★提案の審判はフェアではない
組織をより良く変えたり、ビジネスで良いアイデアを思いついたり、何らかの提案をしたいと思った時、まず考えなければならないことがこの点。それは「その提案が誰の目的にとって正しいのか?」という視点です。その提案は、果たしてあなたの提案を買う人(決定権限のある人)の目的に適っていのか? 自分の目からは重要と思える提案も、実はあなたが勝手に良いと判断しているだけです。動かないルールの1つ目は、決定権限のある人(Decision Maker)の目的次第で判断が為されること。このことをまず忘れてはなりません。
審判が目的の設定や解釈を間違えていたり、あえて意図的に間違えたりすることも少なくありません。意図的に間違えるというのは、審判も自己保存の生物ですから、組織全体としての正しさよりも「審判個人にとっての正しさ」を優先する場合が多々あることを指します。
二律背反においては公ではなく個を優先する人間の性質を理解しておくと、審判は必ずしもフェアではないと最初からわかった上で策を考えることが大事です。
★必要なのは、自分に矢印を向ける覚悟
自分の言いたいことを伝えるのではなく、「自分の言いたいことを相手が買いたいものとして伝えられるか?」という個人レベルの能力。これが提案を仕掛ける側の持つべき「社内マーケティング」のスキルです。
マーケティングの真髄は「顧客視点(消費者視点)で考えること」だと、私はあらゆる機会で力説してきまし。売り手の都合で買わせようと考えても結局は顧客の求める価値と合致していなければ買ってもらえないので目的は達成されません。その時に「消費者はわかってくれない!」と買い手を避難する人間がいれば、とんでもなく間違った認識だと、きっとご理解いただけるかと思います。
自分の部下でそういう勘違いをしている人を見つけると、私はその間違ったマインドセットを徹底的に修正します。その人がプロとして成功するために真っ先に必要なのは、自分に矢印を向ける覚悟です。会社が理解してくれないのは、自分の力が足りないからだと、まずは認める。文句を言うだけで思考や行動が停止する人とは違って、矢印を自分に向ければポジティブな変化が起こります。何が足らなかったのか? 次はどうすれば良いのか? と。自分自身が学んで成長するチャンスを得ることができるのてす。
★組織の目的や戦略に適うかどうか
組織の目的と戦略に合致する提案は通りますが、合致しないものは通りません。前者は「変えられる提案(変えるべきこと)」です。変えるべきでないこととは、組織全体の目的や戦略の観点で見ると正しくないことであり、どれだけ強く主張されようが変えてはいけません。
では、変えられること、つまり変えるべきこととは何でしょうか? それはコスト(≒リスク)とリターンのバランスにおいて、組織の目的や戦略の達成確率を純粋に高くする提案です。
★組織文脈を理解するための3つの切り口
私がオススメしているのは、少なくとも自分が直接続している組織を中心にして、上方向へ1段階(上位組織)と下方向へ1段階(自分の組織の戦略に影響される下位組織)の合計3階層くらいの目的・政略・意思決定者を知る努力を日頃からしておくということです。以下の3つの質問に沿って考えるとわかりやすいことかもしれません。
組織文脈を理解するための3つの質問
(1)自分の属する組織と、上位組織、下位組織、それぞれの目的と戦略は何か?
(2)それぞれの重要事項における意思決定者は誰なのか?
(3)上司と、その上司、それぞれの評価が何によって決まるか?
感想
◆マーケティングスキルこそが日本の企業を救うスキルかもしれない
今回は社内マーケティングの方法の本の触りの部分のみ読書メモとしてシェアしました。
あまりにも内容が濃く、広範囲に渡るので詳しくは本書をお読みください。
さて、まずは著者について少し。
本書の著者である森岡毅さんはUSJをV字復活させた方として有名。
それだけを聞くと、さぞや絶対的な権力をもって、上からの改革をビシビシとしていった方というイメージを持たれそうですが、実は全く違います。
2010年にUSJにプロ・マーケターとして入社。
その後、2012年にCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)として辣腕を振るうことになりますが、それまでの2年間は部長クラス。
そして、CMOに就任しても、上には取締役達がいるわけで、すべて自分の思い通りになる立場ではありません。
そういった環境の中での組織改革、自分の提案を通していくテクニックは非常に参考になると思います。
というのも、著者自身がご自身の改革を
「極めて日本的で、第3セクターから始まった”お役所的”な風潮が随所に残っていて、技術志向も強く、マーケティングや消費者視点という概念からも縁遠い、そんなUSJでも、数年やそこらで、”持続可能なマーケティングができる組織”に変革することができるのか!?」
という課題の実験と言っていますが、かつてのUSJのように思考停止、自己改革力なしといった企業は日本中にあふれています。
バブル以来、かつての超優良企業が凋落していく例は枚挙にいとまがありません。
ダーウィンが「変化に対応できるものが生き残る」と言ったように
企業が消えゆく減少の共通点は、変化し続ける外部環境に適応できなくなること
だと著者は喝破しています。
また、言い得て妙だったのは、著者が企業組織を「人体」に例えているところ。
人体組織は部位のそれぞれの役割が明確で、お互いに「共存関係」になっていますよね。
それぞれがそれぞれの役割でお互いを支え合って、全体が連動して団結している。
まさに理想の企業組織が健康な人体と言っていいでしょう。
そう考えると、たとえばブラック企業などは、体の何処か特定の部分に無理が集中していて、痛みが発生している状態と言えるかもしれません。
そして、日本では「痛み」を感じつつもなんとか我慢して現状を維持しようとしているという企業がほとんどのような気がします。
そういった状態が改善できない企業は、やがて死(倒産)を迎えるわけですが、そうなる前に若い有能な社員が自己改革できる組織は生き残る可能性があります。
ただ、僕も長く社会人をしてきたので、そういった若手をたくさん見てきましたが、大抵の場合、「独りよがりの正義感で暴発して終わり」という結末を迎えて何も変わらないことがほとんどです。
その意気や良し、でも著者の言うマーケティングスキルがないんですね。
いつの時代も変革に突き進むのは若者です。
ぜひ、提案を通すスキル(マーケティングスキル)を若いビジネスパーソンは本書で知っていただきたい。
また、組織のトップは”風通しの良さ”を意識した環境創りに注力してほしいですね。
組織は決定権を持つ「上からの改革」と現場からの「下からの改革」の両輪が噛み合って初めてうまくいもの。
生き残りをかけて組織を変えたいという経営者層も、使命感を持った若手もぜひ読んでほしい一冊。
ちなみに、今年読んだ色々なジャンルのビジネス書の中で、本書は文句なしのナンバーワンでした。
激オススメ。
本書は日経BP社様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
はじめに 一人でも会社に変化は起こせる!
第1部 組織に熱を込めろ! 「ヒト」の力を活かす組織づくりの本質
第2部 社内マーケティングのススメ 「下」から提案を通す魔法のスキル
第3部 成功者の発想に学べ! 起点となって世の中を変えた先駆者たち
終章 マーケティングの力で日本を元気に!
関連書籍
本書中にも登場する同著者の既刊本。
合わせてお読みください。