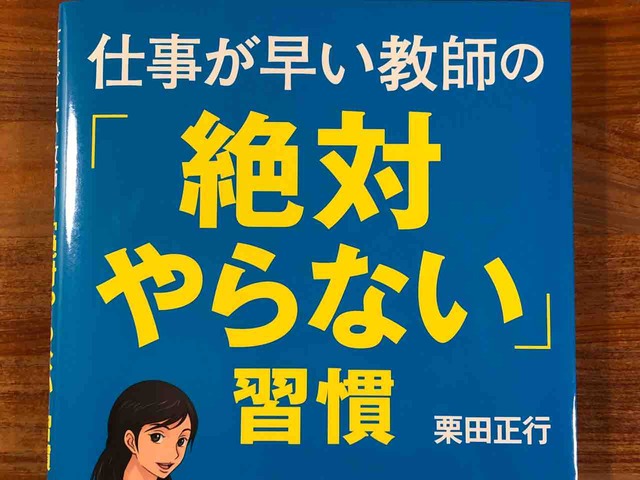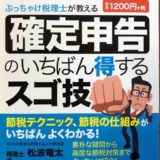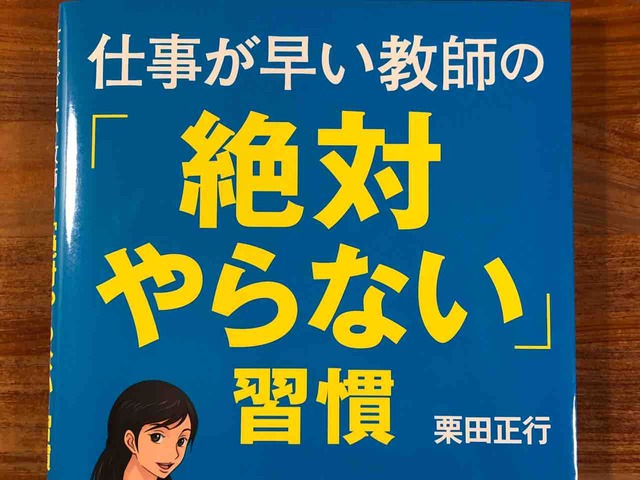
こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。
昨日に続いて今日も栗田正行先生の著書をご紹介します。
こちらが最新刊ですね、『仕事が早い教師の「絶対やらない」習慣』です。
本書では33の「やらない」習慣が紹介されていますが、今回はそれらの大元となる5つの原則をご紹介します。
この5つ、ビジネスパーソンも応用できる内容ですので、ぜひご覧ください。
では早速、気になるポイントの読書メモをシェア!
「やらない習慣5つの原則」読書メモ
★やらない習慣 原則1 残らない・残さない
長時間労働しないことがもたらすメリットは数多くあります。まずは「お先に失礼します」と言える勇気を持ちましょう
「残らない」ことがもたらす、3つのメリット
(1)タイムプレッシャー効果が生まれる
仕事が遅くなる原因の一つに「タイムリミットがない」ということがあります。
もし、あなたが今日は定時に退勤すると決心すると、「定時」という名のタイムリミットが生まれます。(2)疲れが残らない
一番周囲に迷惑をかけるのは、あなた自身が過労で倒れてしまうこと。
自分を大切にすることも仕事のうち。(3)プライベートも大切にできるようになる
仕事以外のことも大切にすると、人としての幅も広がる
★やらない習慣 原則2 教えない
先生であるあなたが情報や知恵を与えすぎると、子どもたちは自分たちで考えなくなってしまう
教えすぎないことは、子どもたちの自主性や成長する力を育てる
★やらない習慣 原則3 叱らない
子供の成長のために、時と場合によっては叱らないほうが良い時がある
覚えておきたいのが、感情のままに「叱らない」という大原則
叱るときのポイント3つ
(1)「行動」を叱る
子供の人格を叱るのではなく、あくまで行動を叱る(2)「ウルトラマン」になって叱る
叱る時間が長ければ長いほど、逆効果(3)叱った後にすぐ「切り替え」をする
叱ったことについて、いつまでも引きずることは百害あって一利なし
★やらない習慣 原則4 つくらない
2つの「つくらない」を意識する
(1)「ゼロ」からくつらない
新しいモノを作る場合、以前作ったモノがないか、あるいは前任者がいるのであればそのひな型があるかどうかを確認します。
もともとあるモノを参考にするというわけです。(2)「自分だけができる仕事」をつくらない
仕事を人に任せることができなければ、その先生は休みを取ることすらできなくなってしまいます。
何かの理由でその先生がしばらく仕事をできなくなったときに、学校全体の業務が滞ってしまうのです。学校としても、個人としても、自分だけしかできない仕事をつくるということはデメリットが多いのです。
★やらない習慣 原則5 付き合わない
自分がやりたいことを我慢してまで先輩や同僚の先生方と付き合う必要はない
ここでいう「付き合わない」とは、決して自分勝手に振る舞うということてはありません。自分にとって大切な人やモノに、最大限の時間やエネルギーを集中できるように工夫するということ
栗田正行(著)『仕事が早い教師の「絶対やらない」習慣』:感想など
◆「残らない・残さない」「つくらない」「付き合わない」の仕事の効率アップと時間確保の基本
今回紹介した「やらない習慣5つの原則」は、いずれも時間を生み出すための原則ですが、内容的におおきく2つに分けることができます。
一つは、「残らない・残さない」「つくらない」「付き合わない」の仕事の効率アップと時間確保のグループ。
もう一つは、「教えない」「叱らない」の育てることを目的も含んだ時短方法です。
まず一つ目の「残らない・残さない」「つくらない」「付き合わない」に関して。
これ、ビジネスパーソンも是非参考にしてほしい。
仕事量が多いとか、ブラックだとか言う前に、もう一度自分の働き方を、上記の3つに照らし合わせて顧みてください。
けっこうこの3つに引っかかるような働き方をしているものです。
そして、僕の経験上この3つは互いにリンクしている場合が多い。
イチから仕事を「つくる」から時間がかかって仕事が「残る」。
仕事が残っているから、残業していると変えるタイミングを逃して他の残業している同僚についつい付き合ってしまう。
このパターンあるでしょ?
すでにあるものをや、先輩の経験・知識をどんどん使えばいいのです。
そして、タイムリミットを設定して全力で取り組む。
若手にとって問題なのは上司や先輩より早く退勤しづらいという点でしょうが、これも多くの場合が本人の気にし過ぎで、たとえ嫌味を言う人がいたとしても、定時に退勤することを実践し続けると、「この人は定時で退勤する人」というイメージができて、だれもあなたが帰ることを気にしなくなります。
(もし仮に、定時で退勤を実践して、上司がそのことを注意するようなら、それは本当にブラックですから早く辞めたほうがいいです。)
ちなみに飲み会もしかり。
僕は飲みニケーションを否定はしませんが、毎回毎回参加する必要はないですよ。
若手は上司に誘われたら断りにくいと思いますが、うまい言い訳を何パターンか用意して上手にかわしていきましょう。
ちなみに僕は育児や妻の都合をネタにしてよく飲み会を欠席しました。
「子供をお風呂に入れないといけないので」
「いま、妻が体調悪いんです」
なんていうのをよく使ったな。
◆「教えない」「叱らない」は管理職の時短方法
本来は「教えない」「叱らない」というのは先生にとって教育的効果を含んだ時短方法ですが、これもそのままビジネスパーソンの特に管理職やチームリーダーなどマネジメントに関わる人にとって使える時短法です。
とはいえ、これはかなりハードルが高いです。
その理由の一つが「教えて君」があまりにも多いということ。
これ、「最近の若いものは」なんてことはいいません。
年齢関係なく、1から10までどころか12ぐらい教えないと動かない人が多いです。
そうなると「自分でやったほうが早いわ!」となりますが、その罠にはまらず、いかに人を育てるかというのは多分教育現場と同じ悩みなんじゃないでしょうか。
そして「叱らない」ですが、これも難しい。
絶対、叱らないといけないときってあるんですよ。
でも、下手に叱るとすぐに「パワハラ」と言われたり、職場に来なくなったりする人がいて、まるごと自分に特大ブーメランが帰ってきます。
ほんとうに管理職受難の時代です。
今回ご紹介した叱るときのポイントを参考に上手に叱ってください。
あと、僕がこれに4つ目を付け加えるなら、「人前で叱らない」でしょうか。
体育会系の部活をやって人以外は、人前で叱られた経験が殆ど無いですから、そういう配慮は必要かと思います。
そして、究極の理想は「転ばぬ先の杖」です。
手間はかかりますが、今の時代は叱るよりも成功体験を積ませてあげるほうが成長するでしょうし、長い目で見るとあなたの時間を確保することになると思います。
以上、感想というより、経験上のポイントを語ってしまいましたが、忙しい毎日でもすこしでも自分の時間を確保して、有意義な人生を送るために、今日から始めてみてください。
本書は著者の栗田正行様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
序章 子どもと向き合う時間を生み出す! やらない習慣 5つの原則
第1章 学校の仕事で「やらないこと」を決める
第2章 先生同士の人間関係で「やらないこと」を決める
第3章 子供との関係や授業で「やらないこと」を決める
第4章 保護者との関係で「やらないこと」を決める
関連書籍
 【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた
【随時更新】現役高校教師栗田正行先生の教師の働き方改革に役立つ全著作とそのおすすめポイントをまとめてみた