
(最終追記:2019年9月11日)
全く驚いた!
8年前にすでに“自炊”していた人がいるとは。
そしてその目指すところは読書家なら誰もが憧れるであろう自分だけのデジタル図書館。
あなたも“プチアレキサンドリア図書館”の館長になりませんか?
皆神龍太郎(著)『iPadでつくる「究極の電子書斎」』:ポイント&レバレッジメモ
★iPad用レザーケース「TUNEFOLIO for iPad」
 |
TUNEWEAR iPad用PUレザーケース TUNEFOLIO for iPad ブラック TUN-PD-000006 (2010/05/31) FocalPointComputer |
このケースは、横にするとiPadをどんな角度にでも立てておけたり、ケースにゴムべルトが付いているので、持ち歩く時に、ぴちっとカバーを留めておくことができたりと、デザイン的にもかなりのスグレものといえる。
だが、デザインや機能よりも、筆者がこのケースを選んだという理由は、次の一点に尽きる。それは、このケースにはキャリング用のストラップが付いているという点だ。
著者はこのストラップをデジカメ用のものに取り換えて、Wiiのリモコンのように手首に固定し、その手で吊革につかまって使用するのだとか。するとちょうどiPadが胸の前に来て読みやすい。
なるほど、見かけの善し悪しは置いとくとして、それなら700グラム前後あるiPadを持って電車で立ち読みしても腕の疲れが防げるし、他のお客さんにぶつかられてもiPadを落とす心配がないですね。
追記:この本ではiPadにデータを入れて持ち運ぶことがテーマですので、こういったケースを紹介されていましたが、スマートフォンが普及した現在は、スマートフォンで代用すればいいと思います。
★「Win Tree」
フォルダの中にあるファイルの名前の一覧を自動で作ってくれる
これは、フォルダの中にあるファイルの名前の一覧を自動で作ってくれるというソフトだ。パソコン上で、Win Treeのアイコンの上にスキャン文庫のデータが詰まったフォルダをドラッグ&ドロップで落としてやると、ファイル名の一覧を一発でテキストファイルにしてくれる。
あとはそのテキストファイルをiPadに読み込ませて検索すればよい。
ワタクシもすでに持っている本を買ってしまうことがあるのですが、本屋さんや古本屋さんで面白そうな本を見つけたときこのファイルがiPadに入っていれば、その場で検索して二重買いを防ぐことができますね。
追記:現在このアプリは販売されていません。
★プラス裁断機 PK-513L
 |
プラス 断裁機 裁断幅A4 PK-513L 26-106 (2009/09/01) プラス |
大きさは42×40×17センチ(重さ12.3キロ)で、A4だと160~180枚を、一撃でさばける。
LEDライトで赤い線が本の表面に投射され切断線をガイドしてくれるのが、なかなか実用的で、かつ格好イイ。
安全で、裁断面もきれいだ。文庫本や新書ならば、セットから裁断までほんの数秒でできてしまう。我らのおすすめの一品である。
難はというと、値段がやや高めなことだろうか。
僕が使っている裁断機です。
とにかく切れ味抜群!女性でも楽々切れて、裁断面も綺麗。
唯一の欠点は、厚さ1.5センチまでしか対応できないこと。
ビジネス書の単行本はほとんどが200ページ前後で、厚さ1.8センチ前後。
「もうちょっとなのに入らない」という本がほとんどなのです。
そういう場合はカッターで本を2分割してから裁断します。
この欠点をカバーし、値段も半額程度ということで本書で言及されている中国製品というのがおそらくこちらの裁断機。
 |
大型裁断機・ペーパーカッター 書籍断裁可 () ペーパーカッター |
中国製の競合製品が出てきた。価格は半額程度である。大きさは38×53×17.5センチと国産と同程度であるが、重さは17キロとやたらに重い。けれどもこちらは一度に400枚まで切れる。
400枚までということは、ほとんどの本がそのまま裁断可能ということでしょう。
しかし、Amazonレビューを見るかぎりでは、結構難有りかと。
油汚れとか、固定が甘いとか、刃の耐久性だとか。
実物を見てないのでなんとも言えませんが、今のところはPK-513Lがオススメかな。
追記:現在、オススメの裁断機はこちら。ハンドルが「押し下げた状態」でロックできて、収納時のスペースが少なくすみます。
★スキャナのいち押しと使い分け
手短に言えば、新書・文庫などはキヤノン、雑誌・カラー本はPFUという使い分けである。
白黒の文字が多い本を素早く読み込み、OCRまで自動でかけてくれるキヤノンと、カラーと白黒を自動判定して、写真や図像を忠実に再現してくれるPFU、という使い分けだ。
著者は「目的に応じてスキャナを使い分けろ」とおっしゃってますが、現実的に購入となるとどちらか1台になるはず。
◇PFU ScanSnap シリーズ ScanSnap
 |
FUJITSU ScanSnap S1500 FI-S1500 (2009/02/07) 富士通 |
こちらは僕が使っているドキュメントスキャナ。
上記のとおりで写真なども美しく読みとってくれます。
ですので、写真の多い雑誌とかあるいは漫画もスキャンしますという方にはこちらがオススメかも。
使用していて感じる欠点は、薄くてツルっとした紙の場合、重送してしまうことが多いという点かな。
その重送に強いといわれるのがコチラ。
◇キャノン imageFORMULA
 |
Canon imageFORMULA DR-2510C 2455B001 (2007/11/06) キヤノン |
僕は使ったことないので感想は言えないのですが、なんと勝間和代さんのご推薦機種なのだそうです。
けど、勝間さんって“自炊”するのかな?
ともかく
でき上がるスキャン文庫の品質を大事にしたいのなら、これらスキャナを1台ずつ持って、使い分けすることをおすすめしたい。
のだそうです。
追記:現在オススメのドキュメントスキャナはこれ一択ですね。

富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1500 (両面読取/ADF/4.3インチタッチパネル/Wi-Fi対応)
- 出版社/メーカー: 富士通
- 発売日: 2018/10/12
- メディア: Personal Computers
- この商品を含むブログを見る
僕も使っていますが、非常に使い勝手いいです。
★PDFリーダーと使い分け
さて、スキャナで取り込んだ“スキャン文庫”をiPadで読む場合、PDFリーダーが必要になります。
しかしこのPDFリーダーに“これしかない!”という決定版が今のところないように思います。
どのアプリも一長一短あるんですよね。
ただ、現在利用できるPDFリーダーのなかでは、やはり著者が推薦する2つに絞り込まれるとワタクシも思います。
そして互いの欠点を補い合うのは、この二つのアプリをうまく使い分けるのが、今のところベターな方法かと。
有料、無料のいくつかのアプリをあれこれ試してみて、結論として私は、「グッドリーダー」(115円)と「i文庫HD」(800円)という2つのアプリを使い分けて、デジタル読書を楽しんでいる。通常はグッドリーダーを使って読書し、本の種類や大きさなどによっては、「i文庫HD」に切り替えるという使い分けをしている。
◇「グッドリーダーiPad版」
「グッドリーダー」は、ipadを代表するPDFリーダーとして有名だ。安いし、とにかく評判がいい。一部では「神ァプリ」とまで呼ばれている。<中略>
グッドリーダーはPDFだけではなく、写真や動画なども再生できる、いわばiPadの「万能ピューワー」といえるアプリだ。PDFだけに限ってもかなり多機能で、反応も速い。
そうなんです。
このアプリ、とにかく動きが軽い!
そして最大の魅力が“検索機能”
電子書籍ならば、全文検索ができて当たり前と思われるかもしれない。だが、それは最初からテキスト形式で書かれていた文書をPDF形式に直したという電子書籍などの場合だろう。元がテキストならば、内容が検索できても当たり前だ。
だが、スキャン文庫の場合はテキストではなく、写真状態の書籍のなかから、画像認識技術を使って活字部分を抜き出し、認識した文字を、元の文章の上にテキストデータとして被せてPDF文書としている。このOCR技術で後から読み込んだ文章の内部まで検索をかけられる、というアプリはめったにない。
この検索機能は凄く便利。
小説やビジネス書の気になるフレーズを検索するのはもちろん、自分の勉強している分野の『〇〇用語集』なんかをスキャンして丸ごと入れておけば非常に便利。
ただ、気になる欠点は機能の表示がすべて英語であることと、画面表示方法に多少難が有ること。
ワタクシとしては本格的に本を読みたい方にはこちらのアプリがオススメ。
◇「i文庫HD」
またi文庫HDは、アップル純正のiBooksが備えている「電子書籍で本を読む楽しさ」が、そのまま再現できるよう工夫されている。
たとえば、指先でぺージの端を押さえてめくっていくと、ぺージが徐々にめくれ上がっていく、というアクションが楽しめる。指先の動きにつれて、ぺージの端が徐々にめくれていくとその途中に見えるぺージの裏側には表側に印刷されている活字がうっすらと裏写りして見え、芸も細かい。<中略>自分で作ったスキャン文庫であっても、同じように「ページめくりアクション」が楽しめると言うあたりが、他の電子書籍アプリにほとんど見られないi文庫HDのすぐれたところである。
この「ページめくりアクション」、そんなにこだわらなければならないことなのかと思われることでしょうが、これがあるとやっぱり本を読んでいる雰囲気が味わえるのですよ。
そして重要な点は次の2点
またi文庫HDは、iBooksで有名になった木目模様の本棚に、スキャン文庫を並べて飾ることもできる。本は題名だけでなく、その表紙や背表紙といったイメージでも覚えているものだ。だから表紙を一望のもとに眺めることができれば、目的の本も探しやすくなる。これはグッドリーダーにはできない芸当だ。
それからi文庫HDは、両面開きの形での表示もできる。「本はできれば、見開きで読みたい」という、読書好きの希望を叶える機能といえるだろう。文庫や新書といった小さな本ならば、iPadを横向きに寝かせて見開き形式で読んでも、そう見にくくはならない。
特に見開きで読めるのがこのアプリの最大の魅力。
見開きで読めて、ページがめくれて、本棚がある。
素晴らしいアプリなのですが、しかし電子書籍最大のウリである“検索機能”がないんですよね。
本当に残念!
それで、「グッドリーダー」と「i文庫HD」の使い分けということになるのですが、そこにはもう一つ問題が。
◇「グッドリーダー」と「i文庫HD」の使い分け
スキャン文庫のデータは、とにかく「グッドリーダー」の中に全部一度入れてしまい、書籍を縦に表示して1ページずつ普通に読む場合や、文書内部を検索したりする場合にはグッドリーダーを利用する。一方、文庫や新書といった小さな本を読む場合には、グッドリーダーからi文庫HDを呼び出して見開きに替えて読む。
iPadのアプリはそれぞれの独立性が高く、同じPDFデータでも、使うアプリごとに記憶させなければなりませんでした。
つまり両方のアプリで読みたいものは二重に記憶させなければならなかったのです。
しかしこれももう上記の方法で解決済み。
当分はこの2つのアプリで大丈夫そうですね。
皆神龍太郎(著)『iPadでつくる「究極の電子書斎」』:感想など
僕も“自炊”しておりますが、とにかく本書は参考になる点が豊富。
【ポイント&レバレッジメモ】ではスキャナやアプリの紹介に終始してしまいましたが、スキャナのちょっとした裏技から、「グッドリーダー」と「i文庫HD」の使い分けなどなど、本書を読んで日頃疑問に、あるいは不便に思っていたことがかなり解消されました。
すでに自炊している方にも買って損はない一冊かと思います。
そもそも著者の皆神さんは2002年ごろから「スキャン文庫」に取り組み始めたのだとか。
その頃の苦労話も面白くて読みいってしまいましたが、フラットベッド型のスキャナしかない時代に試み始めたことに敬意を表したいと思います。
すごい手間だったでしょうね。
なぜそんな手間をかけてまで「スキャン文庫」に取り組んだのか。
それは読書家なら誰でも直面する問題、つまり蔵書の保管スペースの問題が発端。
僕も、知り合いの書評ブロガーたちもこれは頭の痛い問題です。
(先日お会いした女子勉の勉子さんは1年前に買った1200冊はいる書棚がすでにいっぱいになったとか)
これを解決するには今のところ電子書籍化しかないでしょう。
僕もそう思って“自炊”生活を始めました。
するとそこには自然と壮大な計画が浮かび上がって来るものらしく、僕も著者と同じことを考え目指していたことに本書を読んで気が付きました。
それは著者がいうところの“プチアレキサンドリア図書館”であり、蔵書をすべて電子書籍リーダーに収録して持ち運ぶ“ポータブル書斎”なのです。
iPodに所有するCDをすべて収録して持ち運ぶのと同じように、蔵書を常に持ち歩く。
いつでもどこでも本を読むことができる図書館であり、記憶をたどり、調べ物ができるデータベースを携帯する。
ある意味では、理想の書斎を、たとえば立花隆の書斎兼オフィスを凌駕する読書環境を我らは構築したといえる。というのも、「整理分類の手間いらず」&「全文検索の強力さ」&「その持ち運びやすさ」を兼備した情報要塞が誰でも実現可能なのである。
で、それを実現できるiPadなどのデジタル機器がいよいよ出そろってきたというのが今年の状況です。
正直に言えばまだまだ、これらの機器には課題が多数あります。
例えば記憶容量の問題。
著者は64GBのiPadに1300冊のスキャン文庫を収録しているそうですが、それが限界。
キンドルなどはもっと容量が少ない。
また、検索スピードももっと上げてもらいたい。
しかしこれらは性能の問題なのでじきに解決されていくでしょう。
ポイントは“ポータブル書斎”をいかに作り上げ、活用するかだと思います。
ワタクシの様な物覚えの悪い人間にとっては、外部脳として頼もしい“記憶参謀”となる
でしょうが、結局は使い方次第でその価値は大きく変わりますからね。
それともう一つ。
紙だろうがデジタルだろうがそれは本にアクセスする際の手続きの違いであって、あく
までも問題なのは“何をどう読むか”と“それをどう役立てるか”ということ。
読書の本質を見失わないようにすることが重要かと。
【目次】
第1章 蔵書はすべてデジタル化しなさい
第2章 蔵書デジタル化の実践 スキャン文庫の作り方
第3章 デジタル蔵書とiPadで変わる読書スタイル
第4章 「究極の電子書斎」の活用術
第5章 同時に1000冊を読む!「ギガバイト読書術」
あわせて読みたい
【管理人の独り言】
本日紹介した本では、電子書籍リーダーとしてiPadだけが登場しますが、最近キンドル3やガラパゴスなど相次いで電子書籍リーダーが発表されています。
それら「新しいビューワーはどうなのよ?」そして「自炊ってどうやるの?」という方にはこちらオススメ
この1冊で最新の電子書籍関連の情報は網羅できていると思います。





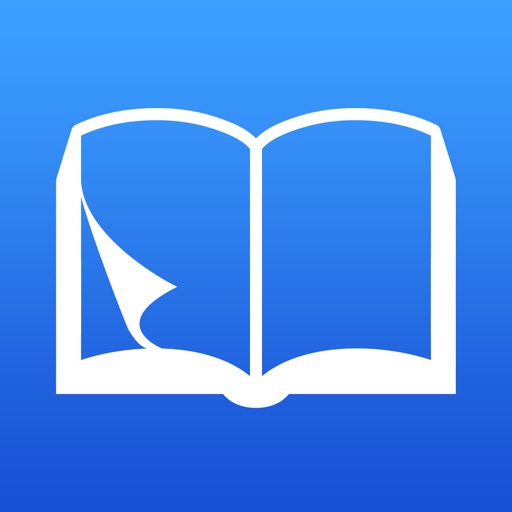
![週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌] 週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Ux6LCXUFL._SL160_.jpg)