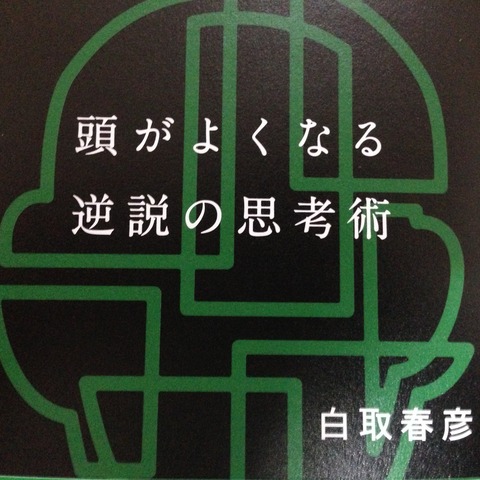おはようございます、一龍です。
新ブログ、最初の書評は白取春彦先生の新刊からスタートすることにしました。
「頭がよくなる」シリーズの今回のテーマは逆説の思考術。
読むと知らず知らずのうちに自分がとらわれてきたものがはっきりと見えだします。
感想など
◆逆説に考えてみる
本書のサブタイトルは「逆説の思考術」です。
白取先生の哲学的視点から、主に生き方論、人生論が語られていますが、さすがに”逆説”とつくだけに、読んでいて私自身もガツンとやられることが多々ありました。
しっかり自分で考えて生きているつもりでも、あまりにも漫然と生きているなぁと。
そして、丸くなりかけている自分自身を、再び尖った部分を引っ張りだす、そんな刺激に満ちた本でした。
◆哲学とは自分を開放すること
本書を読んでみて、私の中に浮かび上がってきたキーワード、それは「開放」でした。
私たちは知らず知らずのうちに様々なものに縛られて生きています。
たとえ、「人生を自分の力で切り開いてきた」、「自分は自由に生きている」という人でも、ジョブズ風にいうと「誰かの人生を歩んできた」人がほとんどではないでしょうか。
これは日本人の国民性なのでしょうか。
人の目を気にしたり、世間の常識の枠内に納まろうとしたりということを、無意識のうちにしてるものです。
それが悪いこととは思いません。
その意識のおかげで世のなかがお互いに住み良くなっているという面もあるでしょう。
ただ、あまりにそれらを気にして、単にこじんまりと人生をまとめてしまうのはあまりにもったいない。
自分で自分の人生を「まぁ、こんなものでしょう」と諦めてしまうことを、「足るを知る」という考えを引用して納得させるのは、なにか違うような気がします。
全方位尖っている人は、おそらく変人扱いされ、この世の中は生きにくい世界となるでしょう。
要はどの部分で尖るか、どの部分は丸くなるか。
そのバランスだと思うのです。
そしてその尖る部分を自分で決めていくのが自分の人生を生きるということなのではないかと思い至りました。
ところで、
この本は当然白取先生の哲学的思考をベースに書かれています。
今回本書を読んで、哲学とは小難しい思考をこねくり回すものというイメージから、実は自己の開放のためのツール、思考であると再認識させられました。
いや、間違っていたらゴメンナサイ。
ただ、哲学って実学なんだなと(←こんなこと言うと余計に白取先生に怒られそうですが)。
◆何かになり続ける人生を
さて最後に、いくつもの印象的な言葉と出会えた本書ですが、最後にすごい言葉が出てきます。
「安心など死ぬまでできない」
どこかに安心があると思っているから、宗教とか、大企業とか、人は何かに頼ろうとするのですよね。
人間は弱い生き物に例えたのはパスカルですが、彼はその一方で人間にしかない強さも見出していました。
どうせ死ぬまで安心できないのなら、そうと割り切ってしまいましょう。
そして人間独自の強さを発揮しましょう。
ではどんなとき人は強くなれるのか。
それはきっと目標に進んでいるときでしょう。
「何かになろうと、変わり続ける努力をし続ける」
たとえ死の1秒前であっても、そういう姿勢であり続けたいと思います。
読書メモ 心に残った言葉
★創造的に生きる
たくさんの選択肢があるのだからわたしたちは自由だと勘違いしているのだろう。いくら選択肢があったところで、所詮それは両脇がフェンスで制限された道に過ぎない。その制限をそっと行い、わたしたちの生き方を操作しているのは統治体制、時代風潮、その時代特有の考えかたや価値観(エピステーメー)だ。
そのフェンスを超えて外に出てしまうと、非倫理的だと非難されるだろう。あるいは異常だとか、落伍者だとみなされる。では、そのフェンスの上に立って、フェンスを危なっかしく揺らしながら進めばどうだろうか。
何の比喩かというと、創造的に活きるということだ。
★貧しい人生とは主体的でない人生だ
ところが、収監されていなくても自由に主体的に生きていない人がいる。その人たちにとっても毎日はつらいものになっている。誰がそういう人たちかというと、日々を服従と反応だけで生きている人だ。<中略>
それがよい生き方ではないのは、かれが心の奥で感じとっているつらさが証言している。人生がつらいのではない。その人が自分の人生をないがしろにしているからつらく感じるのだ。そこに増殖するのは貧しさという黴ばかりだ。
★自分の可能性を狭くしない
わたしたち各人が固有の性格や性向を持っているとするのは、妄想や架空の物語を信じることにひとしい。現実をよく見た方がいい。人はその場においていくらでも変わりえるものだ。<中略>
人間はそういうふうに性格として固定された存在ではけっしてないのだから、手人や自分の性格についてくよくよと思案したり、慮ったりしないほうがいい。
さらに加えるべきは、もっと迷信度が深くて、自分の思いと行動を結局は世間的で矮小にしてしまうくだらない事柄、要数rに星座だな血液型だの十二支だの字画数だの運命学などが語る妄言をも、目や耳に入れないことだ。
そうしないと、わたしたちの可能性が狭まってしまう。それは自分を小さくすることだ。そうさえしなければ、人は何にでもなれるのだ。何でも自由にできる。揚々たる可能性が眼前に開けている。
縛りさえしなければ、人は最高の可塑性を持った万能年度なのだから。
★何かになり続けるのが人間だ
何かになり続けることが実はその人をその人らしくしているのだ。それなくしては、ただの人間でもなく、奇妙な生物にすぎないだろう。
要するに、人は「成る」ことができるが、「持つ」ことはできない。<中略>
19世紀の哲学者ニーチェは「人は生成する」と考えたが、その生成こそ人を人たらしめている。
自己実現化するのではない。あらかじめ固定された自己などない。何かに成るという運動を継続している存在が人なのだ。
★自尊心を棄てよ
やっかいなのは自分の感情ではなく、自尊心というやつだ。そして、この自尊心の中身は、本当に自分に対しての尊敬ではなく、自分をよく見せたい、自分の能力はもっと高いはずだ、という見栄ばかりだ。
だとしたら、つまらない自尊心は棄ててかまわないだろう。そしてその代わりに持つべきは、矜持であろう。
★安心など死ぬまでできない
安心の社会。安心して働ける社会。そんなものは、自分の給料さえ貰えばいいと思っている能無しの考えた愚にもつかない標語にすぎない。実際には、誰もが死ぬ寸前まで安心にたどりつくことはできないだろう。<中略>
生きることはすべて不安なのがあたりまえ。だから、うまくいったときは大笑いできるし、感動も深くなるのだ。それが人間ではないか。
目次
1 人生を破壊する方法
2 方法論を求めるな
3 小事と大事を区別せよ
4 安心など死ぬまでできない
今日ご紹介した本
本書はDiscover21社様より献本していただきました。
ありがとうございました。
関連書籍
白取春彦先生のこちらの本もどうぞ!