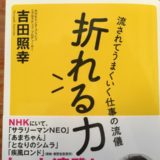おはようございます、一龍(@ichiryuu)です。
先日、現役高校教師栗田正行さんの著書、『「発問」する技術』をビジネスシーンでも役に立つとして紹介しまた。
ぜひ管理職、マネジャーの方は参考にしていただきたいと思いますが、今回はさらにビジネスシーンで実際的に部下を育てるのに役立つ質問(発問)の方法を、芝本秀徳さんの著書、『誰も教えてくれない 質問するスキル』 からご紹介したいと思います。
今回の紹介記事では、第4章 問いかけで「人」を育てる より、部下に成果を上げさせる6つのステップのポイントをピックアップしました。
部下に成果を上げさせる6つのステップのポイント
★部下に成果を上げさせる6つのステップ
部下に成果を上げさせる6つのステップの構成は次のようになっています。
STEP1 要求(期待)を伝える
STEP2 問題を課題化する
STEP3 プロセスをモニタリングする
STEP4 リアルタイムにフィードバックする
STEP5 結果を評価する
STEP6 次のビジョンを設定する
以下にそれぞれのステップを紹介していきます。
★STEP1 要求(期待)を伝える
1つめのステップは「要求(期待)を伝える」です。企業で仕事をしている限り、すべての行動は、会社が求めるもの、期待するものでなければなりません。しかし、会社や上司が自分に何を求めているのかは、「驚くほど」伝わっていないものです。
<中略>
自分では伝えたつもりでも、驚くほど伝わらない。それが上司の要求なんですね。だから、マネジャーは、会社や自分が何を求めているかを、折りに触れ、何度も何度も伝えないといけない。要求は伝えないとわかりません。「そんなこと言わなくてもわかるだろ」というのはマネジャーとしての怠慢です。
★STEP2 目標と課題を設定する
要求を伝えたら、次に「目標」と「課題」を設定します。目標とは「ギャップをどれくらい埋めるか」です。「問題=ギャップ」は、一気に埋められるわけではありません。あまりに大きすぎる問題に取り組むと手に負えません。なので「いつまでに、どれくらい」ギャップを埋められるかを設定するのが目標です。
<中略>
「目標=埋めるべきギャップ」を設定したら、今度はそれを課題化します。問題の課題かとは、言い換えれば問題解決のアプローチを考えることです。行動可能・実行可能なテーマに分解するのです。このとき「こうすればできるだろう」と指導してしまうと、せっかくの考える機会を奪ってしまいます。
考えるきっかけを作る問いかけの具体例
「このギャップを生み出している要因は何が考えられる?」
「このギャップを埋めるために、どんなアプローチが考えられる?」
「この問題を解決するために、必要な材料やスキルは何があるかな?」
「最初に何から手をつける?」
「何か私に手助けできることはある?」
★STEP3 モニタリング
目標と課題ができたら、そのあとは本人の様子をモニタリングします。モニタリングとは「見続けること」です。
<中略>
目立たないように自然に助けるには、普段からコミュニケーションを取っていないとできません。いきなり上司に「ちょっといいか」と会議室に呼ばれても、緊張するでしょ。それよりも、普段の会話の中で、次のように呼び水を指してあげるのです。「どう? 順調?」
「何か問題はない?」
「何か困ってることはない?」すると「いま、こういうことで行き詰まっています」とか「こんな課題がありまして」という話を聞くことができます。
言い換えれば、モニタリングとは「日々のコミュニケーション」です。普段、まったく部下と話をしないで、1ヶ月に1回のミーティングで部下の状況を把握することはできません。進捗会議や月次報告のミーティングなどは、やはり「公式の場」であるという意識が働きます。公式の場で、普段思っていることや困っていることを相談できるはずがありません。
★STEP4 リアルタイムなフィードバック
先ほど、「日報には返信してあげるといいですよ」と話しました(本書参照)。これはフィードバックです。マネジャーとしていまの部下の状況をどう見ているかを、リアルタイムにフィードバックしてあげる。
<中略>
上司が「このままで大丈夫だよ」「少し軌道修正した方がいいよ」と教えてあげるのです。直接的に教えるのではなく、できれば部下に自分で気づいてほしいですね。ここで使えるのが「アクナリッジメント(承認)」です。これは部下がやったこと、できていることを「事実として認める」ことです。
<中略>
「アクナリッジメント(承認)」は、自分がしてほしいと思っていること、自分が導きたい方向に向かう行動を見つけ、それを認めてあげることです。「お!報告書の期限を守ったな」
「お!メンバーによく声をかけてあげているね」
「お!会議で発言したな」この「お!」という事実を伝えてあげる。褒めるよりも「事実を事実として認める」ことが大切です。
★STEP5 結果を評価する
区切りになれば、例えば3ヶ月とか半年に1回、もしくはプロジェクトのスタート時、完了時などに、それまでの期間について、部下といっしょに評価します。「上司が部下を評価する」のではなく、「武官といっしょに、その期間の活動を評価する」ことが大切です。
<中略>
対象となるフェーズなり、プロジェクトの「活動」について反省ではなく、文字通り「振り返る」のです。このとき、よく使われるフレームワークが「KPT」です。
Keep:うまくいったこと、今後も継続すること
Problem:うまくいかなかったこと、改善すること
Try:次にやってみたいことマネジャーは一方的な評価を伝えるのではなく、部下本人にその期間の自分自身の取り組みとその結果をどう捉えているかを聞くことから始めます。
★STEP6 次のビジョンを設定する
取り組みと結果について評価ができれば、そこで一区切りがつきます。プロジェクトもそうですが、この「区切り」が大切です。うまくいったとしても、いかなかったとしても、そこで一旦区切る。そうすることで、次への行動が取れるようになります。
<中略>
区切りがついて、次への行動への意志が湧いてきたところで、次のビジョンを設定します。「次のプロジェクトではチームをどうしたいか?」
「1年後、自分はどうなっていたいか?」
「そのために、まず何から手をつけるか?」ビジョンを設定すれば、それに基づいてコミュニケーションを取ることができます。
感想など
いかがだったでしょうか。
今回紹介したのは著者の芝本秀徳氏が経験の中から築き上げた問いかけで人を育てる道筋で、本エントリーでは本文から大量に引用ているように感じるかもしれませんが、ほとんど流れを紹介している程度にとどまっています。
実際には紹介した各ステップごとに更に細かいコツがあり、また、「強みリスト」や「日報」といったツールの使い方も紹介されています。
どうか、興味を持たれたら本書に直接当たって、細かい部分まで確認していただきたいと思います。
さて、4月といえば新年度の始まり。
ニュースでもいくつかの有名企業の入社式の映像が流れました。
こういったときに経営者は理想の社員像として
「自ら考えて行動する社員」
を必ず挙げます。
これは就活の場で欲しい人材の理想像としても語られます。
ところが実際に働き始めると、「自ら考えて行動する社員」を育てるシステムや環境は整っているわけではありません。
大抵の場合、上司に通常のマネジメントの中で人材育成しなさいよと丸投げされているのが現状ではないでしょうか。
人手不足の折、プレイングマネージャーとして自らも一線で走らなければならない人も多いことでしょう。
人を育てるというのは「我慢して待つ」ことが強いられるものですが、こういった余裕のない状況の中でついつい我慢しきれずに「代打、俺!」となってしまうかもしれません。
しかしそれでは人材は育ちませんし、部下も面白くもないでしょう。
今回「部下に成果を上げさせる6つのステップ」を紹介したわけですが、あらためてキーポイントとなるのは、
”上司がどれだけ我慢できるか”
であると再認識しました。
もっとも、上司というのは基本的に常にプレッシャーに晒され、孤独で不安なもの。
しかし、なぜ不安なのかちょっと考えてみてください。
上司が不安になる原因の一つは、何がどうなっているか、どれくらい進捗しているか見えてないからではないでしょうか。
この状況、もうおわかりだと思いますが、きっと不安になるようではあなたと部下とのコミュニケーション量が足らないことを示しています(というか、マネジメントできていないということです)。
具体的な声かけ(質問)とともに、ふだんの業務をこなしながら状況を知るための日報の活用方法など、マネジメントの参考になる具体例も豊富な本書。
もしあなたが不安な上司ならぜひ本書を活用してほしいと思います。
本書は著者の芝本秀徳様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
まえがき
第1章 質問するスキルの効用
第2章 質問するスキルの4要素
第3章 問いかけで「要求」を引き出す
第4章 問いかけで「人」を育てる
第5章 問いかけで「議論」を深める
参考文献