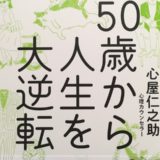こんにちは、一龍(@ichiryuu)です。
今日ご紹介するのは明治大学の齋藤孝先生の監修による『1分間武士道』です。
もちろんベースは新渡戸稲造による『武士道』で、各項目を1分で読めるようになっていて、ビジネスパーソンがそのエッセンスを学びやすく編集されています。
これまで何冊か武士道のエッセンス本を読んできましたが、あらためて本書を読んでみると、現代のビジネスパーソンに通じる哲学が流れていることに気づきます。
その一端をご紹介したいと思います。
なお、訳文は日本近世史家で東京大学大学院教授、および東京大学史料編纂所教授でもある山本博文氏の『現代語訳 武士道』(ちくま新書)からとなっています。
では早速、ビジネスパーソンにも通じる武士道のエッセンスを読書メモからシェア!
『1分間武士道』から読書メモ
★責任が人を磨く
「武士道は、語句の意味で言えば、戦う騎士の道、ーーーすなわち戦士がその職業や日常において守るべき道を意味する。ひと言で言えば、『戦士の掟』、つまり戦士階級における『ノブレス・オブリュージュ noblesseoblige』(高貴な身分に伴う義務)のことである」
★他人を責めず自分を変えよ
「人を相手にせず、天を相手にして人事を尽くし、人を咎めず、わが誠の足りないことを反省せよ」という西郷隆盛の言葉を新渡戸は述べています。
★ムダを省くと仕事は優雅になる
「何かをしようとするなら、それをするための最良の道が必ず存在するはずである。その最良の道こそは、最も効率的であるとともに、最も優雅な道である」と、礼儀作法について新渡戸は述べています。
★批評するより行動するのが武士の職分
「サムライは、本質的に行動の人であった。学問は、その活動の範囲外にあった。武士は、その職分に関係ある限りで、学問を利用した」
★加えるな。そぎ落とせ。
武士が愛好する茶の湯について、新渡戸は「趣味を最高に洗練することが目的であり、わずかな拒食さえも宗教的嫌悪を持って追放される」と述べています。
なぜなら「茶の湯の必須の要素である心の平静・・・振る舞いの静けさと落ち着きが、確かに正しい思考と正しい感情の第一条件である」からです。
★命がけとは生きて戦うことだ。死ぬことではない。
「おおむね屈辱に対しては、人はただちに憤激し、死をもって報復した。それにひきかえ名誉は・・・人生最高の善として貴ばれた。富や知識ではなく、名声こそが青年の追求すべき目標だった」
★自分を試せ。道は開ける。
「真の名誉は、天命を成就することにあり、それを全うしようとして招いた死は決して不名誉ではない。これに反して、天が与えようとするものを避けるための死は、実に卑怯である」と新渡戸は述べています。
武士は死を恐れてはなりませんが、いたずらに死ぬことは勇気ではなく、臆病だとされました。志を成就するために、恥を忍んででも懸命に生き抜けというのが武士道です。
感想
本書では、武士が備え、実践すべき7つの徳として
義=卑怯や不正を憎む心性
勇気=正しいことのために行動する
仁=弱者や敗者に対する寛容さ
礼=他人を思いやり、地位に敬意を払う
信と誠=嘘やごまかしを絶対にしない
名誉=武士が最も希求したもの
忠義=目上の者への服従と忠実
が紹介されています。
実は、本書を読むまで、現代の日本人の精神にとって武士道というのはもう関係がない、ピンとこないものだと思っていました。
しかし、あらためて考えると、こういう徳目はまだまだ日本人の中に生きており、行動規範となっていますよね。
この国の多くの人が武士ではなかったにも関わらず、国民性に昇華されているような気がします。
現代は多様性の時代ですので、武士道精神に凝り固まる必要は僕は感じませんが、多様性の時代だからこそ、一本芯となる精神というか、背骨のようなものが必要だというのも感じます。
祖先が残してくれた大きな遺産として、武士道精神を心の根底にもっている、腹の底に置いている。
そういう生き方はいいのではないかと思います。
本書はSBクリエイティブ様からご恵贈いただきました。
ありがとうございました。
目次
まえがき
1 責任が人を磨く 武士道とは何か
2 他人を責めず自分を変えよ 仕事の心得
3 批判するより行動する 志とは何か
4 加えるな。そぎ落とせ 覚悟の心得
5 平伏さずに心服させる 組織人の心得
6 命がけとは死ぬことではない 死生の心得
7 貧富を忘れて生きよ 処世の心得
8 人は能力より人格ではかられる 品格とは何か
9 自分より大きな何かを守る 誇りとは何か
参考文献
関連書籍
同シリーズには孫子の兵法もあります。
今後も「1分間〜」シリーズとして続いていくんだろうか?